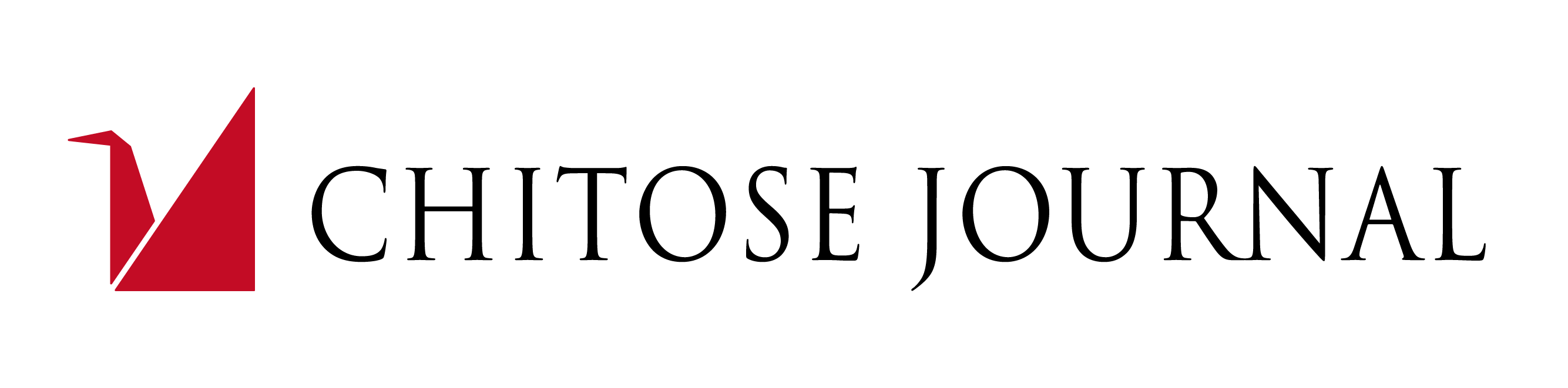確か2000年だったと記憶していますが、Nature誌の一般記事の中に『ヒトゲノムの全塩基配列が今日発表されました。このニュースを見て、ヒトについて、貴方の理解が深まりましたか?』という記事が出ていました。ある学者は、『一晩明けたけれど、何も変っていない。』という意味の返事を返していました。あれから25年、多くのヒト遺伝子が同定されその機能の解析も進んでいますが、未だにその状況は変わりません。このNature誌上でのやり取りは、分子生物学者にとっては大きな警告と受けとる必要があります。このままの方針で研究を続けていっても、いつまでたっても、人とは何か?と言う問いに答えられない可能性が非常に高いのです。
DNAに始まり形質発現に至る遺伝情報の流れに関する研究には、それぞれのステージごとに、ゲノム(Genome)に因んで、研究内容を示す言葉の末尾に “-ome”が付されています。例えば、Transcriptome(mRNAやtRNAのような転写物の研究)、Proteome(タンパク質の研究)、Metabolome(代謝物の研究)のように。言うまでもなく、この研究方法は情報伝達の分子機構の解明という点では合理的です。世界的プロジェクトであるヒトゲノム計画は1990年にアメリカで始まり、私企業も参加して2000年に無事収束し、上記の様に全塩基配列が決定されました。しかし、“遺伝子(遺伝情報)と生命体の間をつなぐものは何か?”という、生命科学者が長らく探し求めてきた大命題には未だに答えられていません。今後、遺伝情報のネットワークが全て明らかになったとしても、この研究方法からはヒトの形体ですら説明できないのではないかと危惧しています。形態ですら、と書きましたが、おそらく、生体の外形ほど分子生物学的に記述困難なものはないと思っています。例えば、新型コロナウイルスの場合、遺伝情報やたんぱく質の相互作用は殆ど解明されていますが、この情報だけからウイルスの外形を予測するのは極めて困難であり、電子顕微鏡に頼るしかないでしょう。一体何が欠けているのでしょう?
本コラムのタイトルである“遺伝子と生命体の間をつなぐもの”という大命題に挑戦したのは、おそらく19世紀の進化学者ラマルクが最初でしょう。進化は古くから最も人を引き付けてきた生命現象の一つです。遺伝子の存在すら未だ曖昧な時代に、ラマルクは遺伝と進化の間をつなぐことに挑戦しました。ラマルク進化説の代名詞になっている“用不用”や“獲得形質の遺伝”という用語は、内的な進化駆動力の存在をイメージすることなしには浮かんでくる言葉ではありません。時代が余りにも早すぎたせいか、進化の駆動力を生む内的実体の同定には至りませんでした。
この問題に関して、近代の研究者は手を拱いていたわけではありません。J.ケアンズ博士(1922-2018)とA.クラー博士(1947-2017)は遺伝情報源としてのDNAではなく、物質としての2重らせん構造に注目しました。クラー博士は筆者の友人でもあり、不均衡進化理論の強力な支持者でもありました。
J.ケアンズ博士は、変異の入っていない古い一本鎖と、多くの変異が入っている新しい一本鎖が存在することに注目し、マウスの小腸幹細胞が一生のうちに1000回もの分裂を繰り返しながらもがん化しにくいのは、変異の最も少ない最も古い鎖を保持し続けるためだと説明しました。ところで、幹細胞から分化した小腸上皮細胞は分裂しながら最終的には腸管内に便と一緒に放出されます。従って、例えこの分裂が原因でがん化したとしても、小腸がんはめったに観察されない理由を実にスマートに説明しました(文献1)。
一方、A.クラー博士は、DNAの2重らせんを形成するW鎖とC鎖が全く違う物質であることに注目し(塩基の相補的関係で両鎖の塩基組成は全く異なります。このことに気付くだけでも非凡な能力の持ち主であったことが分かります。)、両鎖の物質としての違いを認識するたんぱく質の存在を予測し、W鎖とC鎖が体の左右を決める因子として機能するというSSISモデルを提唱しました(文献1,2,3)。左右逆位などの遺伝的疾患の解析から、両鎖の物理的差異を区別・認識し、身体の左右を決定する遺伝子の存在を予測しました。
両博士に共通する点は、DNAの塩基配列に関係なく、DNAの物質としての特性を認識する分子機構が存在し、生命体の構成や振舞いに直接関係するという、卓越したアイデアを持ちあわせていたことだと言えるでしょう。両博士に対する評価は、がん化の防御システムや、内臓逆位の原因の解明という矮小化されたものになりがちです。しかし、この2つの研究は生命科学の研究に正しく一石を投じたと言えます。その理由は、幹細胞の存在意義は全ての組織や器官の成り立ちに共通する基本的仕組みであり、左右対称性の決定は、多細胞動物の成体形作りに関わる根源的な事象だからです。
情報という用語は社会活動や通信工学で使用されます。情報は受けとる側のシステムの初期値によって結果が大きく異なります。例えば、野球チームの監督の発する言葉も、その時の選手の状態=初期値によって反応が全く違うように。最初DNAから出た遺伝情報は、上述した、各omeのステップの道のりを通って次から次へと伝わります。しかし、このままの状態にしておくと、まるで伝言ゲームの様に、段階が進むにつれてますます制御できない状況に落ち入ります。
命題である“遺伝子と生体の間をつなぐもの”を発見するためには、情報系の流れの中に、何か“レール(軌道)”のようなもの(構造生物学的実体と表現すべきでしょうか?)を噛ませて、乱れた情報の流れを整理する仕組みが必要になります。この“レール”は生体内に求めるべきで、生体外に求めると、既にダーウィンの自然選択圧という名解答が待っています。J.ケアンズとA.クラー両博士は期せずして、DNAの分子構造に “レール”の機能がある事を見出したのです。ここで重要なのは、物質としてのDNAは構造的に安定であり、遺伝情報に直接左右されないことの認識です。このテーマで、J.ケアンズ博士・J.ワトソン博士・A.クラー博士と筆者の計4名で、東京シンポジウムを開く計画を立てましたが(2005年)、提案者であるA.クラー博士(J.ワトソン博士の元ポスドク)が69歳で急逝され、実現には至りませんでした。
1995年1月13日、J.ガードン博士の紹介で、共同研究者の土居洋文博士(当時、富士通)とケンブリッジ大学・地球科学部・進化古生物学教授のサイモン・コンウェイ=モリス博士を訪ねました。博士は読者もよくご存じの、カンブリア爆発説を唱えた方です。訪問の目的は不衡進化理論について討論することでした。3人で大学の講義室をお借りして、最初に筆者がスライドを使って30分ほど話しました。博士は化石の専門家であるにも関わらず、質問は分子生物学に関するものばかりで、教養の深さに感銘しました。ご質問の内容から推察して、こちらの話の内容はよく伝わり、十分にご理解納得していただいたと感じました。
その後、筆者は1999年に講談社から英文の不均衡進化理論に関する書籍を出版し、博士にはその書評をお願いしました(文献4)。最近、その書評を読み直す機会があり、博士の当時のご意見と筆者の現在の考えがとてもよく一致している事に気付き、取り急ぎ本コラムに寄稿した次第です。以下に、博士の英文の書評の邦訳を一部変更して掲載します。
『………不均衡進化理論が正しいとすると、進化の仕組みを理解する助けとなるばかりではなく、進化の道のりの方向転換や生物分類の配置転換が起こるかもしれない。さらに重要なのは、不均衡モデルが環境変化に柔軟に抵抗する内的な進化の駆動力の存在を示唆している点だ。おそらく、これこそ長い間研究者が探し求めていた、遺伝子と生命体の間をつなぐものだ。そして内的な進化の駆動力と適応の最適化の実体ついて議論を呼び起こすだろう。この理論は分子生物学の範囲を超えた深い意味をもつであろう。』
特に太字で強調した箇所は、四半世紀前に書かれたものとはとても思えないほど的を射ています。正直言って、当時、筆者はここまでこの問題を詰めていませんでした。最後のくだり、『この理論は分子生物学の範囲を超えた深い意味をもつであろう。』は、不均衡進化理論が高校国語の教科書の教師用参考書に取り上げられた事で、博士の予測は当たっています。参考書にとり上げた理由として、過ちや失敗の中にこそ真理が隠されていると主張し、日本の中・高等教育が生徒に正解ばかりを求めていることに強い警鐘を鳴らしています(文献5)。
筆者は以前から、進化の原因を生物側に求めている点で、ラマルクの進化説や木村資生博士が提唱した分子進化の中立説には少なからず心を惹かれていました。その証拠に、本コラムの各号のタイトル欄にラマルクのことが書かれています。当時も今も、筆者の目標は進化に通底する基本原理の発見と、その数理的表現です。
現時点で、我々が提唱した不均衡進化理論は次のようにまとめることができます。DNAから出る遺伝情報を整理する“レール”の実態は、DNA複製装置(複製中のDNAと複製関連酵素群との複合体)であり、活きた遺伝アルゴリズムとして、適応という名の最適化問題を解きます。その上、これまで均衡変異に付きまとってきた、変異の閾値(Error threshold)という足かせを取り除くことが出来ました。そして、今まで想像も出来なかった広大な新規適応地形の出現・展開に成功しました。この適応地形の上では、理論的には、まるでマジックのように超変異率の下でも元の遺伝子型の存在を許容する条件を自由に設定することが可能です(文献6,7)。私たちは、不均衡変異の場をDisparity quasispecies(不均衡準種)と呼んでいます。
このように、遺伝子情報と進化の間をつなぐ“レール”の実体が、DNA複製装置であることが明らかにされました。この発見の切っ掛けは、複製で生じた2匹の娘DNA間の変異率の差(Fidelity difference:FD)を導入したことでありましたが、今日の結果は発見当初からある程度は予測できました。しかし、生体内に進化を駆動する分子装置(活きた遺伝アルゴリズム)が存在し、具体的な形で提示できるとは想像していませんでした(文献6)。
今年も不均衡進化理論の完結に向けて頑張りたいと思います。また、新しい“レール”探しも始めたいと考えています。
2026年1月14日
古澤 満
文献:
- Furusawa, M (2024). Implications of double-stranded DNA structure for development, cancer and evolution. Open Journal of Genetics, 1, 78-87. Open Journal of Genetics. doi:10.4236/ojgen.2011.13014.
- 分子生物学の新しいパラダイム[第18回 古澤満コラム]
- 天才遺伝学者、アマール・クラー博士逝く[第35回 古澤満コラム]
- Furusawa, M. (1999). 『 DNA’s Exquisite Evolutionary Strategy』Kodansha Ltd., Tokyo.
- 不均衡進化理論と高校国語教育[第53回 古澤満コラム]
- 古澤満.情報文化学会誌. 30巻1号, 3-10. (2024). 『不均衡進化理論 ―日本発の科学理論―』
- 古澤満「不均衡進化論」筑摩選書(2010)