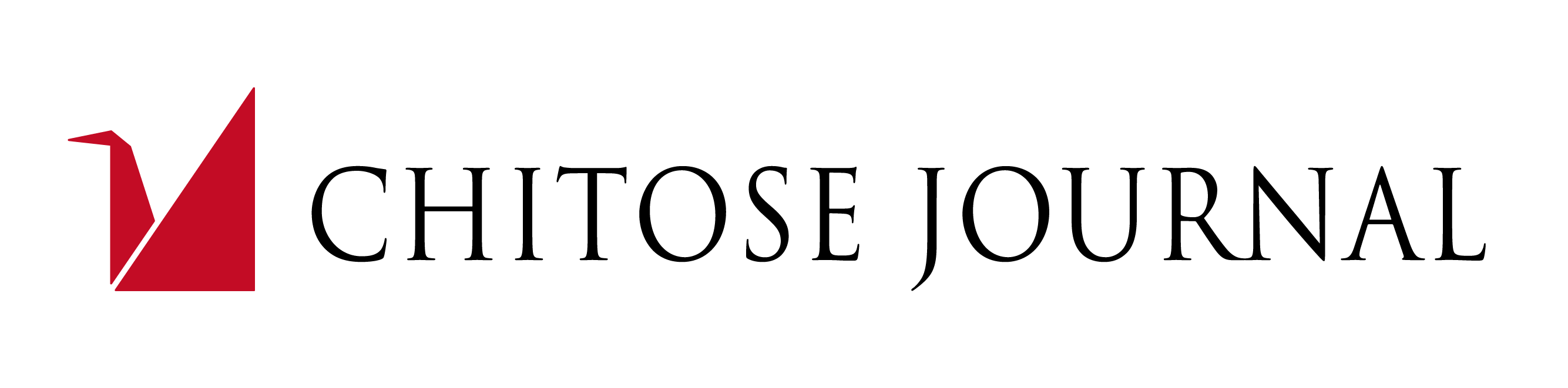筆者らが不均衡進化理論を公表してから早30余年の年月が流れました。この辺りで一度、世界の進化論の流れの中での本理論の立ち位置を自己検証しておきたいと思います。
実を言いますと筆者は進化の専門家ではありません。大学では発生生物学を学び、がん細胞の再分化や細胞工学の研究を行ってきました。また、DNAやRNAを実際に取り扱った経験もありません。不均衡変異に気づいた当時は、こののち生物を材料にして研究を進めるのか、それとも理論研究に徹するかを随分悩みました。既に60代に入った年齢や研究費の問題もあって結局は理論研究の方を選びました。ところが困ったことに、筆者は遺伝学や進化理論の専門知識に欠けるばかりか、理論研究に一番大切な数理的取扱いの基礎知識が足りないことに初めて気付きました。この欠陥を埋めるために、先ずは当時、東京大学大学院 薬学系研究科の院生だった内村有邦博士(発生・遺伝、公益財団法人放射線影響研究所)、合田徳夫博士(情報科学、株式会社日立製作所)、洪実博士(当時、慶応大学医学部。Elixirgen Therapeutics社)をはじめ皆様方のお力をお借りして、自主会合を東京で持つことにしました。
第一製薬(現、第一三共株式会社)を退職後、西宮の自宅に戻ってからは、明石基洋博士(遺伝・進化、成蹊大学)と藤原一朗博士(数理、大阪産業大学)の3名でグループを作り、専らPCや電話を使って遠距離研究を続けています。尚、最初の論文の数理部分を担当いただいた土居洋文博士(当時、富士通株式会社。株式会社セリッシュエフディー)、共同研究者で夭折された数理に強い青木和博博士(当時、ネオ・モルガン研究所(現ちとせ研究所))に感謝いたします。
ご承知のように、世界の進化研究の主流(ネオ・ダーウィニズム)はダーウィンの自然選択説とメンデルの遺伝の法則の統合の上に成り立っています。つまり、平均して起こる突然変異が生殖と染色体交叉によって集団内へと広がることを前提として理論が立てられています。そして、環境により適応した変異を持つ個体が新しい種として定着し進化すると説明されています。
しかし、ネオ・ダーウィニズム的解釈では説明し難い事実が生物界には散見されます。一例を挙げてみましょう。ヒトの親子のゲノムDNAをシーケンスし比較した結果、両親から子に約70個もの変異が伝わることが分かっています(文献1)。変異の3%が有害や致死変異であるとしますと、ヒトは世代ごとに平均2個の有害遺伝子を背負うことになります。比喩的に言えば、ヒトは一生の間に2度死ぬと表現してもよいでしょう。では何故、我々人類はぴんぴんと生きているのでしょう?このようなナイーブな質問に即答できないのは、当該理論そのものに根本的な欠陥があると疑ってみるのが常道です。ネオ・ダーウィニズムの立場からこの現象を説明するのにどれだけ苦労しているかを知りたい読者は、筆者の総説をお読みください(文献2)。
それでは、ダーウィンやメンデルが間違っていたのでしょうか?いや、そうではありません。自然選択のアイデアや遺伝の法則の発見は、正しいというより寧ろその慧眼に驚かされるばかりです。両巨頭が活躍した18世紀には、未だ神による生命創造説が蔓延り、DNAはおろか遺伝物質の存在も明らかにされていませんでした。ダーウィンやメンデルにこの責任を負わせるのは筋違いというものです。筆者は1930年以降に発展した所謂、集団遺伝学(ネオ・ダーウィニズム)にこそ、その責任が問われるべきものと考えます。1世紀もの長きに亘って、世界中の錚々たる学者によって築かれてきたこの本流の学門に、筆者らが不均衡進化理論の中で指摘してきたようなシンプルで本質的な見落としが起こり得るのでしょうか?俄かには信じ難いことです。
本コラムのシリーズの中でも繰り返し不均衡進化理論を紹介してきました。今ではネオ・ダーウィニズムとの違いを一言で表現することができます。不均衡進化理論の本質は、2匹の子DNA間の変異率の差(FD=fidelity difference)という新しい変数をネオ・ダーウィニズムの概念の上に付け加えた点にあります。
FDを考慮したときの変異の地形は次のようになります。
2匹の子DNAの一方の変異率が0に限りなく近く、トータルの変異率が優位に高い場合を仮定します。世代を繰り返しても依然として変異率0の元のDNA(遺伝情報)が無傷で残り、同時に多くの変異を抱えたDNAが出現します。つまり、前者で元本を保証し、後者で多様性を創り出すという訳です。このように、今迄誰も想像もしたことのない変異の地形が開けます。
ネオ・ダーウィニズムの誤りは、変異が基本的に集団の構成員に平均して平等に入るものと仮定した点にあります。この仮定に基づきますと、ゲノム当たりの変異率が複製(世代)ごとに略1を超すとエラー・カタストロフィーを起こし、集団は自滅の危機に晒されます。所謂、変異の閾値と言われるものです。従って、進化はごくゆっくりと進まざるを得ません。このようにFDを導入することの一番の効果は、変異の閾値が上昇または消失するため進化の可能性が飛躍的に増大することにあります。進化はダーウィンが想像したように、常にゆっくりと進むものではありません。自動車のようにFD値を変更することによって速度を自由に変えることができるのです。
FDを考慮することによって、進化に関するよくある質問には明快に回答することができます。以下にその例を示します。
- 短期間の高変異状態が予測されるカンブリア爆発や、キリンの首が突然長くなった化石上の事実。
- 断続平衡現象。進化は長期間の緩やかな変化を伴う時期と、短期間で急変化する時期の繰り返しであるという化石上の事実。
- ダーウィン進化の理論を演繹すると、生物種間の区別がはっきりしないものになると予測される。しかし、現実の生物界では種間の区別はくっきりとしている。不均衡進化理論の帰結である“元本保証と多様性拡大効果” に従うと、種分化は飛び飛びの現象であり、事実を矛盾なく説明することができる(文献3、図4-5b)。
- 定向進化(進化は一定の方向に向かって継続して起こるという説)は“元本保証の多様性拡大”の必然的な結果と捉えることができる(文献3、図4-5b)。
- シーラカンスのような生ける化石の存在。不均衡進化の“元本保証”の当然の結果として説明可能。
- がん細胞は正常細胞に比べて変異率が異常に高いにも関わらず、エラー・カタストローフによる自然治癒が稀なのは、がん細胞のFDが高いからだと説明される(文献4)。
注:分子進化の中立説と不均衡進化理論はそれぞれ進化の違った側面を見ているもので、相互に排他的関係にはないと考えられる。
これ迄説明してきたように、複製系(自分を残し新しいコピーを作って増殖する現象)は単なる増数・増殖とは違って特異的な変異の場(地形)を創り出します。その場を生み出す因子がFDです。FDが存在するおかげで、不滅の進化戦略(“元本保証の多様性創出”)が生まれてきたと解釈できます。極言すれば、岩石と比べてかくも弱々しい体を持つ生物が地球上で繁栄し進化し続けることができたのは、FDの存在によると言っても過言ではありません。尚、宇宙全体を見渡しても、複製する物質は素粒子を含めて生命以外には存在しない事実も留意すべき点でしょう。
不均衡進化理論の立場からしますと、進化駆動のエンジンはDNA(RNA)の複製装置そのものであり、適応という名の最適化問題を解く優秀な遺伝アルゴリズムとして作動し、そのガソリンはFDであると喩えることができるでしょう。更に、ラマルクが暗示した生物体内に存在するであろう進化の駆動力を生み出す実体の一つがFDであるとも表現できるでしょう。
一科学者としての筆者の目標は、生物進化の裏側に流れる共通した法則を発見し、出来ればそれを数理的に表現することでした。この意味では、FDの発見によって一応の目的は達せられたと思います。八木健博士(大阪大学大学院 生命機能研究科)をはじめ、幾度となく討論の機会をいただいた皆様に、この場を借りて御礼申し上げます。
時々夜中に突然目が覚め、われわれの理論が間違っているのではないかと反復反省することがあります。その度に思い起こすのは哲学者A.ショーペンハウエルの言葉、『初めは無視され、次に足を引っ張られ、最後には当たり前だと言われる』です。新しい概念を発表したときの述懐の言葉です。私たちの現況はまさしくこの名言の二番目の段階にあります。やはり最後には『当たり前だ』と言われるのでしょうか?
2025年9月25日
古澤 満
文献:
1 A. Kong et al. Rate of de novo mutations and the importance of father’s age to disease risk. Nature, vol 488, pages471–475 (2012). doi: 10.1038/nature11396.
2 Furusawa, M. The disparity mutagenesis model predicts rescue of living things from catastrophic errors, Frontiers in Genetics 421, 1-8 (2014). doi: 10.3389/fgene.2014.00421.
3 古澤満.「不均衡進化論」筑摩選書(2010)
4 Furusawa M. The role of disparity-mutagenesis model on tumor development with special reference to increased mutation rate. Journal of Solid Tumors, Vol. 3, No. 4, 22-31 (2013). doi.org/10.5430/jst.v3n4p22.