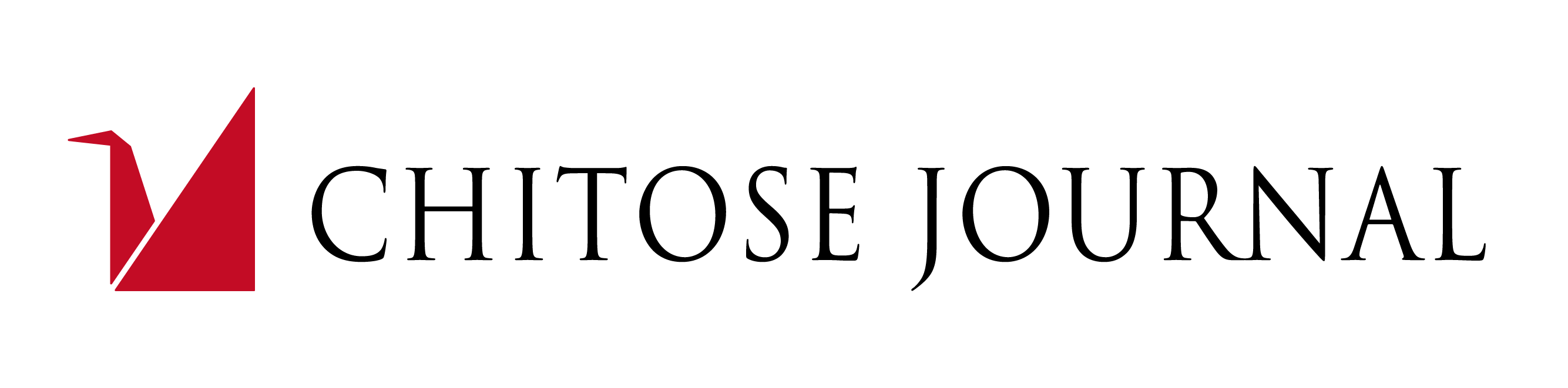19世紀に進化研究者ラマルクとダーウィンが現れました。前者は進化の概念を初めて提唱し、進化の原動力を生物自体に求めたのが特徴です。一方、後者は進化の原動力を変異体の自然選択に求めたのが特徴です。ご承知のように、現在では集団遺伝学を主流にしたダーウィン派に軍配が上がっています。ラマルクの魅力溢れる“獲得形質の遺伝”の考え方は、遺伝子の実体が不明な当時としては卓越した概念であったと思いますが、未だ確証は得られていません。尚、今日でも“獲得形質の遺伝”を証明したとする論文が時々報告され、その人気は衰えていません。
ところで、ラマルクのように進化の駆動力を生物側に求めるのはむしろ自然な成り行きだと思います。何故なら、進化する本体は生物自体であることには間違いないからです。筆者も早くから生物側に進化を駆動する確固たる未知の分子装置があるに違いないと考えてきました(文献1, 2)。そうでないと,最初に地球上に現れた単細胞生物が、いくら~40億年経ったとはいえ、ダーウィンが言うように自然選択だけでヒトにまで進化したとはとても思えないからです。
筆者は先ず原点に返り、何が生物と物質とを区別しているのかを考えることから始め、生物の特徴は“複製”にあり、との結論に達しました。素粒子を含めて宇宙にある全ての物質の中で、複製するものは生物以外には見つかっていません。この点は友人の物理学者に確認をとっています。
この立場から既存の進化論を見直しますと、多くの研究は“増殖”(集団の構成員の個数が増えること)と“複製”(元を残して同じものを作ること)を区別せずに混同して使っているようです。今から考えると少し不思議なことですが、1953年にDNAが発見された後のネオ・ダーウィニズム(総合進化説)においてさえ、DNAの複製の分子機構を基盤にした進化理論は見当たりません。
やがて筆者は、1968年に発表されたDNA複製時に見られる岡崎断片の生物学的存在意義の重大さに気付き、不均衡進化理論に行き着きました。その経緯は文献に委ねることにして(文献1, 2)、理論のキーワードである不均衡変異(disparity mutagenesis)の言葉の定義と、それが進化に及ぼす効果を以下に簡潔にまとめておきました。
(1)DNAの複製の結果生じる2匹の子DNA間に生じる変異率の差を不均衡変異(FD: fidelity difference=忠実度の差)と定義する。
(2)不均衡変異のコンセプトの下では、変異の閾値(最大許容変異率)は上昇する。
(一方の子供が変異率~0であるような極端な場合には、閾値は消失し、集団内に変異がいくら入っても集団が滅亡しない特異領域が形成される。)
(3)典型的な不均衡変異の世界では、一度現れた遺伝子型の存在は理論上系統樹内に永久に担保される。
(集団の平均変異率とは無関係に、”遺伝情報の元本が担保された多様性拡大の実現”が理論上可能になり、進化にとって理想的な場が形成される。)
以上のように、既存の変異の概念に、新しい項(変数:FD)を一つ加えるだけで進化の景観(変異の地形)はガラッと変わります。それは今まで誰も想像したことのない世界で、複製に付随する特質と考えられます。変異は正規分布する、という常識はもう通じません。即ち、正確な遺伝(変わらないこと)と多様性の創出(変わること)という一見矛盾する2つの事象を同時に具現化できる特殊な場が現れます(文献3)。
最初にこのことに気付いた時、目から鱗が落ちる感覚を体験しました。筆者らが探し求めていた、生物に内在する進化駆動機構に違いないと思いました。つまり、DNAの複製装置に内包されている不均衡変異遺伝アルゴリズムが進化の駆動力を生み出すエンジンの実体であり、そのエネルギーはFDである、と表現できます。
筆者らが長年探し求めてきた大進化を引き起こした実体がFDであるという可能性があり、19世紀初頭に提出されたラマルク進化説の現代的表現の一つであると信じています。この思いに達したのは著者の思い上がりだけではありません。ノンフィクションライターの最相葉月氏、カンブリア爆発の化石研究で有名なケンブリッジ大学のサイモン・コンウェイ=モリス教授も拙書の書評で、不均衡進化理論とラマルクの関係を直接、或いは間接的に述べておられます。両氏は口を揃えて、この理論は驚くほど単純なので物議を醸し出すだろうが、おそらく正しいであろうと言及しています(文献1)。
さらに想像を逞しくすれば、FDは自動車の変則ギアのようなもので、進化の速度と方向性を調節するキーファクターであり、コンウェイ=モリス教授も指摘するように、環境制御とうまく組み合せれば人為的な進化の方向付けが可能になるでしょう(文献1, 3)。
2025年4月22日
古澤 満
文献:
1 古澤滿『不均衡進化論』筑摩書房 (2010)
2 不均衡進化理論―日本発の科学理論―
3 Fujihara I, Furusawa M. Disparity mutagenesis model possesses the ability to realize both stable and rapid evolution in response to changing environments without altering mutation rates. Heliyon. 2016;2(8):e0014. DOI: 10.1016/j. heliyon.2016.e00141