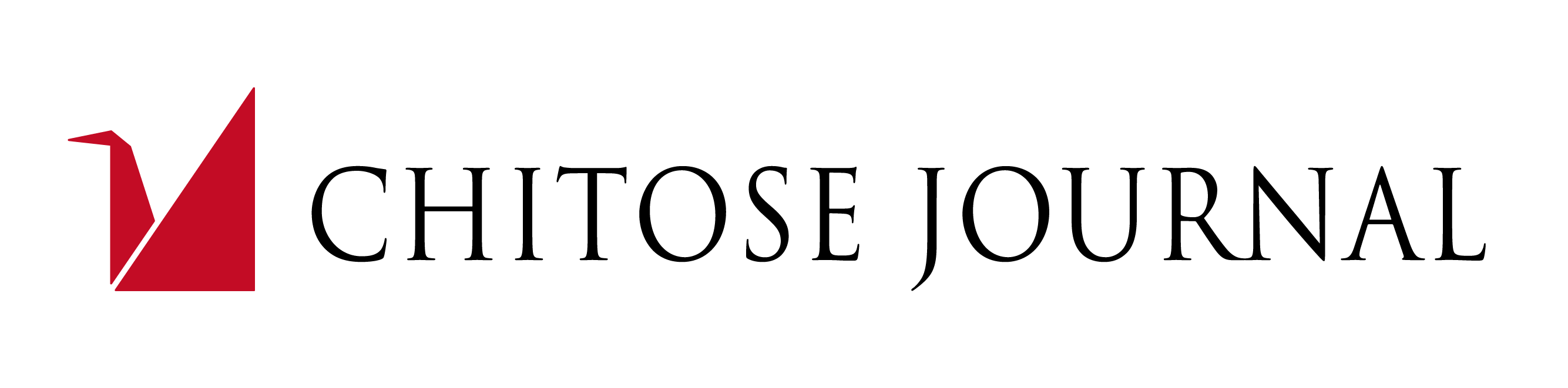私は漫才が好きだ。
出来るだけ心残りのないように、毎日全力で生きていたいと思っているのだが、それでも幾つかある人生の心残りの一つが、「若い頃に真剣に漫才の練習をしなかったこと」だ。どんなに漫才が好きでも、自分で真剣に努力してみないことには、その肝の部分がわからないと思うからだ。
44歳の私は、大好きな漫才師の名前として「やすきよ以降」の大勢の漫才師の名前を(ヤホーで調べるまでもなく)何組でもあげることができる。そんな大好きな漫才師達の中で、何年たってもそのネタの詳細まで思い出せるのは「上手なフォーマットを生み出した漫才師」だと思うのだ。型とか枠とか言ってもいいが、本稿ではフォーマットと呼ぶことで統一する。(欧米か)
漫才における優れたフォーマットとはなにか。第一は、漫才師二人の会話が次はこう進むはずだという予測を、聴衆にしっかり共有させやすいことであり、第二に、共有したその予測を一定のパターンの下でずらしながら話を展開させやすいことである。「しっかりとした共有」と「パターンの下でのずらし」を様々な角度で繰り出す事ができるのが優れたフォーマットであり、優れたフォーマットを生み出し、共有とずらしをしっかり演じることができる漫才師が天才なのだと私は思う。(チョットナニイッテルカワカラナイ。)
私は、こうしたフォーマットを生み出し、演じることができる漫才師をとても尊敬している。しかし一方で、日々の自分の仕事の中で自社の若手メンバーが「一般的にこういう時には、こうするもんですよ。」と得意気になって裁くような仕事の仕方をしているのを見るとどうにもこうにもその仕事に向かうスタンスに嫌悪感が押さえられなくなることがある。
何故ならば、仕事と言うものは同じように見えても、毎回毎回必ずどこかが違うものだし、その「何処かが違うところ」を味わうことも仕事の楽しさの一つであると私は思うからだ。
目の前にある課題をフォーマットに載せて右から左に裁くような仕事の仕方をしていると、もしかしたら大事なポイントだったかもしれない小さな差異を見逃すかもしれない。また、そんな仕事の進め方の中で、新しい発見や気付きが生まれることは絶対にない。「仕事を覚えた」という言葉で満足し自分の幅を狭めていくような仕事の仕方をしているメンバーを見ると「そんなことを毎日やってて楽しい?」と思わず問うてしまうのだ。
私が身内として、「常識をなにも知らない新人」や「自分を凄い人だと勘違いしているような奴」や「世の中と折り合いの付け方がわからずに病んでる奴」と好んで仕事をしたがる(その結果、色々な人に迷惑を掛けてしまう)のも、仕事をフォーマットに乗せようともしない彼らとともに仕事をしながら、私自身が常に新しい気づきを得たいからということが大きな理由である。
面白さを追求したいという動機は同じなのに、何故、私は漫才ではフォーマットに敬意を抱き、仕事ではフォーマットに嫌悪を感じるのか。
漫才は、新たにフォーマットを生み出した漫才師に対して敬意を抱き、仕事の場合は、どこかの誰かが作ったフォーマットに、自分の仕事を乗せようとしているから嫌悪を抱くことが理由なのだと思う。
つまり「仕事のやり方というフォーマットに乗せて、仕事を裁くような仕事のやり方」とは、言ってみれば他の漫才師が作ったフォーマットを模倣して、劣化版の漫才をしているのと同じであると感じるからだ。
他人が作った漫才を真似しただけのものを見せられるくらいなら、自分で考えたつまらない漫才を見せられる方がずっとマシだというのが私の考え方なのである。
もちろん、そんな理想論を掲げても、我々の日々の仕事の全てに対して新しいフォーマットを産み出すことはかなり難しい。難しいだけでなく、既にお決まりのフォーマットの上で仕事をしないと仕事として認められないどころか違法になる場合もあるし、セキュリティの問題も起こりうる。だいたい、お決まりのフォーマットを構築して、多くの人に同じフォーマットの上でやってもらうことと、ビジネスのスケールアップが同義であることも多い。
そもそも漫才だって、二人の間に大きなスタンドマイクを立てその両側で立ち話をするという大きなファーマットが存在する上で、若者たちが新たなフォーマットの構築に挑戦している様が好きだと言っているわけで、私もなにも全ての仕事に対してゼロからフォーマットを作りたいと言っているわけではない。どんな創作活動も大枠としてのフォーマットが決まっているからこそ、その中で新しいフォーマットを産み出す創意工夫を楽しめるものだと思っている。
我々の事業を作っていく中で、多くの人から敬意を抱かれるような「フォーマット」を一つでも多く生み出していきたい。そのためにも、我々にとっての「守らなければいけない既存のフォーマット」と「生み出さなければいけないフォーマット」の境界線がどこにあるのかを今後も考え続ける先に、何かとてつもなく大事なことが待っているように思えてならないのだ。