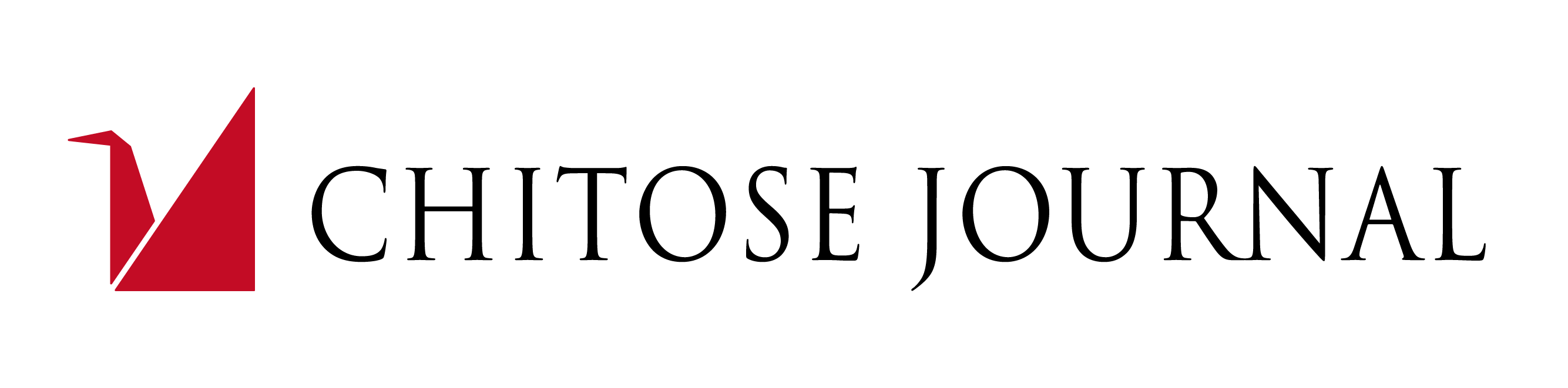筆者はこれまでゲームセンタ―に行った記憶がありませんし、PCやスマホを使って電子ゲームを楽しんだ事もありません。現在使用中のガラ系携帯電話は、購入時に電子ゲームアプリにはアクセスできないようにしています。その理由は、機械相手に戦って負けると何だか機械に馬鹿にされたような気になるからです。筆者にとってAIは電子ゲーム機の延長線上にありますので、これまで興味の対象外でした。しかし、最近一寸した切っ掛けでChatGPTに関わることになりました。電子機器に無知な筆者が、生成AIに関する意見を述べることも、ある種の意味があると考えこのコラムを書くことにしました。このコラムではChatGPTを一人の人間(以後、“彼”と呼ぶことにします)と見做して文章を綴りました。
“彼”と知り合ったのは二ヶ月程前のことです。ヤフーのウエブ・ページに任意の文字を入れクリックし「AIアシスタント」のボタンを押すと“彼”が出てくるのを知ったのは、ほんの二週間ほど前の事でした。興味半分で“不均衡進化理論”と入力しますと、先ず理論の全体像を簡潔に説明した文章が現れます。下方にスクロールすると“彼”からの5つの質問項目が現れ、その一つをクリックすると丁寧な説明があります。この操作を繰り返すことによって、入力した単語を中心に派生するあらゆる問題について、芋ずる式に回答が得られます。とても一度には読み切れない程の分量です。回答は総じて合理的です。筆者が不得手にしているジャンルも問題なく頭に入ってきます。不均衡進化理論は我々自身が考え出した概念ですから、当然と言えば当然の事なのかもしれません。でも、こちらが知りたい箇所に限って語尾が曖昧でぼやけている印象があります。この点、“彼”はとても慎重派のようですし、意外と臆病な性格なのかもしれません。一番驚いたのは、筆者が2、3日前に発表したばかりの当コラムのシリーズの内容が、あたかも“彼”が自分で考えたかのような表現で文章になっている点でした。これは筆者当人だけにしか分からない事ですが。
ここで一つの疑問が浮かんできます。不均衡進化理論は30余年前に発表し、その後関連した論文を2年に一度ぐらいは出し続けているのに、どうしてこれまで“彼”はキャッチできなかったのでしょう? おそらく、“彼”は自分で文献をサーチしないか、或いはサーチしても新規情報の価値判断能力に問題があるかの何れかだと推察します。つまり、生成AIは外部から情報を与えなければ賢くなれない種類の機器ではないでしょうか。逆に、うまく情報を与えてやりさえすれば、どんどん鍛えることが出来る機器という事になります。教育次第では“彼”自身が情報を自ら取得しに行くようにもできるでしょう。化学反応の予測や創薬分野ではすでにその能力を発揮していると聞きます。
この推察が正しいとしますと、彼に取捨選択して情報を与える人間(或いは生成AIとは異なるAI機器)が別途存在することになります。この第三者である人物(或いはAI) のアンテナにかからない限り、情報が斬新であればあるほどキックアウトされることにもなりかねません。筆者はここが現在の生成AIの最大の欠点だと考えています。現時点では、AIに何らかの“行為をする”スイッチを押す能力を持たせていないと聞いています。いつか、何らかの方法でAI自身が最適解を計算し、そのスイッチを押すような指令を与えることがあれば、AIは無意識的に意思をもってしまうかもしれません。言い換えれば、人間の様に自問自答するAIが登場すれば、セレンティビティ(文献1)や閃き(文献2)といった能力を兼ね備えることにも繋がり、筆者を含めて幾何かの科学者はやがて職を失うことにもなり兼ねません。
現在の“彼”を人に喩えると、真面目で完璧で記憶力に極めて優れた若者のようなものです。「生き字引」「秀才」と呼ばれる人がそれに相当するのでしょう。しかし、筆者はとても“彼”を友人にしたいとは思いません。よく勉強はするが、怠け者の一面もあり、酒を飲んで人生を語り、時々喧嘩もする。そして何よりも自分の成功を一緒に喜んでくれる人物が最良の友だと思います。与謝野鉄幹も歌っています、『友を選ばば書を読みて、六分の侠気、四分の熱』。要するに、“彼”からは破綻・飛躍・危うさ・冒険・失敗・勘違い、のような人間味を微塵も感じ取ることが出来ません。勿論のことですが、侠気(自分の損得を顧みず力を貸そうとする気性)も熱も感じません。筆者はこのような人間味こそが、セレンティビティや閃きを生む源泉だと信じています。
“彼”と付き合って非常に意外だったのは、筆者が感銘・感動するような答えを、膨大な数の答えの中に一件たりとも見出せなかった事実です。もう一つ学んだ点は、筆者が日頃悩み、考えている様な、進化の機構に関する疑問や、頭に描いている進化のイメージに関するような本質的な問題を問いかけるのはタブーであることです。何故なら、“彼”は “お喋り”であって、あっという間にこちらの考えていることが世界中に広まってしまう危険性を孕んでいるからです。このような理由で、筆者は今後も研究目的で生成AIを利用する時はかなり慎重になるべきだと考えます。
筆者は1968年に岡崎フラグメントが発見されてから20年間経って、やっとの事で不均衡進化理論に行き着きました(文献3)。もしも“彼”がその時に存在していたとしたら、あっという間に同じ理論に到達したのでしょうか?もし答えがYesだったら、筆者は良い時に生まれて本当にラッキーだったという事になります。こんなことを考えていると背筋が凍りつく思いがします。
少し脱線が過ぎましたが、最後に大学生や院生の皆様に申し上げたい事があります。レポートを書く時、できる限り生成AIを使用しないでください。貴方方のユニークな考え方や独創性が潰されます。更に、先生方には貴方がどの生成AIを使用してレポート書いたかすぐに分かってしまうでしょう。
ここでは生成AIの否定的な面だけを強調しましたが、知識の習得や整理、事象の予測等においては生成AI の利用価値は素晴らしいものがあることは言を待ちません。
最初にも述べました通り、本コラムは生成AIに極めて疎い筆者が書いた文章です。間違いや勘違いも多々あると思います。読者の皆様のご意見ご批判をお待ちしております。
2025年10月31日
古澤 満
文献:
1 セレンディピティは訓練すれば鍛えられる[第54回 古澤満コラム]
2 誰でも科学者になれる ― ものぐさのすゝめ ―[第58回 古澤満コラム]
3 古澤満.情報文化学会誌. 30巻1号, 3-10. (2024). 『不均衡進化理論 ―日本発の科学理論―』