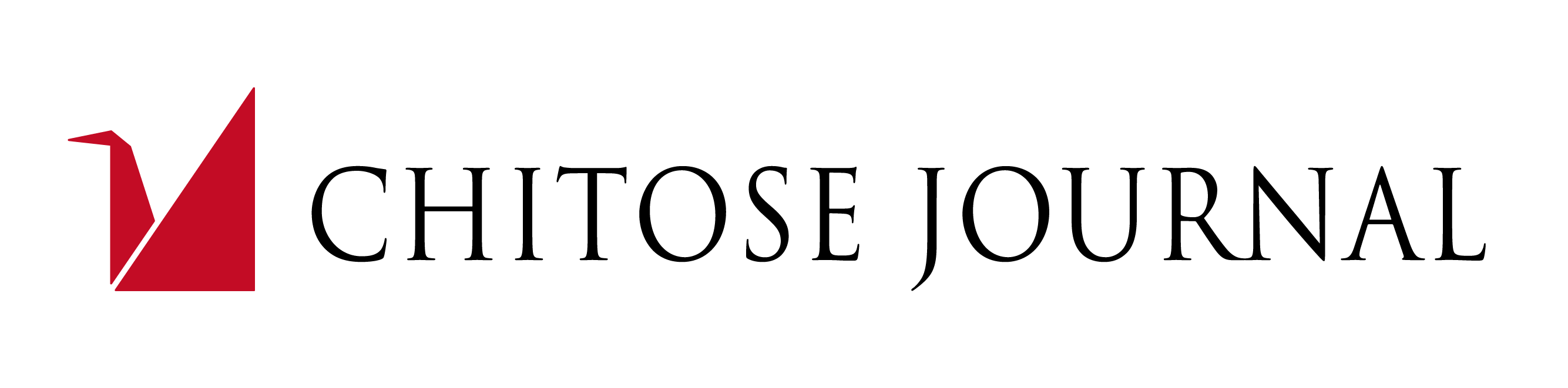科学者になるためには免許状も許可証も学歴も必要ありません。大学教員の場合も基本的には同様です。従いまして、法律的には誰でも科学者になることができます。これが科学の世界の一番良いところです。慶応から昭和にかけて活躍した、かの有名な和歌山出身の博物学者、南方熊楠翁の最終学歴は東京大学予備門(旧制大学の予科に相当)中退ですが、生涯Nature誌に生物学と天文に関する51報もの学術論文を出しています。
ところで読者の皆様、唐突ですが、人類最大の発明・発見とは何かご存じですか?アインシュタインの相対性理論、エジソンの白熱電球、ベルの電話?いやどれも偉大ですが、違います。正解は車輪です。人類が重い荷物を何とか楽をして運ぼうとして考え出した代物で、その出現は紀元前3500年のメソポタミア文明に遡ると言われています。車輪には2つの大きな特徴があります。軸受けの部分はなるだけ抵抗を少なくし、現代では主にベアリングが用いられています。一方、余り指摘されない点ですが、円形の車輪は地面と殆ど1点で、或いは一線で接するため、その部分が変形するほどの力が掛り、巨大な摩擦力が発生して空回りを防ぎます。この摩擦力がないと、線路の上に油が撒かれたり昆虫の幼虫の大群を引き潰したりした時のように、機関車の動輪がスリップして前に進むことが出来なくなります。車輪は本当にすごい発見です。
ここから一つの教訓が生まれます。人類のなるべくなら楽をしたいという“ものぐさ”な性格こそが科学を生み出した大きな力なのです。そう言えば、すべての運搬手段や交通機関、通信技術、さらには経済金融システムも人類特有の“ものぐさな性格”の賜物だと言えるでしょう。
科学者ではない読者の方々には、観察・研究対象として生物進化を推薦します。何故なら進化は我々生き物自身の問題ですし、なにせ億年単位の事象ですから、実験的に証明することが甚だ困難だからです。寧ろ、逆にこのような難問題にこそ誰もが解決するチャンスがあると考えるべきでしょう。専門家にはないナイーブな目で進化を見れば、今まで誰も気が付かなかった進化の一面を捉えることが出来るかもしれません。もしそのチャンスがやって来たら、何も遠慮することはありません。今はSNSの時代です、専門家にどんどん質問することをお勧めします。
進化の中でも、今でも筆者にとって一番の謎は昆虫の擬態です。恐らく、昆虫の擬態に興味を持ったことがない方はおられないと思います。
10年程前に、日本中から数人の生命科学者と2名の文筆家に大阪の北に集まっていただき、フランス料理を頂きながら『擬態ワイン会』なる怪しげな名前の会を開きました。討論の内容を、私見を加えてコラムにまとめました(文献1)。この機会にお読みいただければ幸いです。
主に流体力学と相対成長理論の観点から擬態を論じてみました。相対成長というのは、19~20世紀に活躍したダーシイ・トンプソンが提唱した説です。すべての多細胞生物は特有の幾つかの基本構造からなり、それぞれの基本構造の相対的成長によって形(種)が決まるという誠に魅力ある説です。当時、ありったけの知恵を絞ってコラムを書きましたが、残念ながら擬態の本質には全く迫ることができませんでした。
その後、若干の進捗がありました。昆虫は脊椎動物と違って開放血管系を持っています。私たちの体の様な毛細血管系では無いので、動脈から出た血液は体組織の間に滲み出て静脈へと移動します。つまり、血液は一枚の外皮を隔てて直接外界に触れています。何かのヒントになりますでしょうか?また或いは昆虫の複眼と脳には見たものを自分の体に具現化する3Dプリンターのような未知の機能があるのでしょうか?そうとでも考えない限り、枯れた木の葉の葉脈や虫食いの跡まで真似ることはできないと思うのですが。
昆虫の擬態のような摩訶不思議な現象の解明には、最初の“閃き(ひらめき)”が大切です。閃きは個人の経験や知識と現実の現象とをどのように結び付けるかにかかっていると想像します。その結合に科学的論理性を求めるのは見当違いです。しかし、閃きと言っても無(む)から有(ゆう)が生じる訳はないでしょう。脳にインプットされた記憶同士の偶然の結合が閃きを生むと考えますが、その結合の非論理性こそが問題解決の鍵となると思います。
生成AIも予めインプットされた情報(記憶)の結びつきを利用しているところは脳と似ていますが、論理性を旨とするAIとは異なり、閃きの方は非論理的に記憶同士が偶発的に結合することによって生まれるものと考えます。つまり、記憶の非論理的結合こそが人間の能力の特徴だと思います。閃いた後は専門家の助けを借りて仕事を進めればいいわけです。
勿論、擬態もDNAの配列情報からアプローチする方法があります。しかしあまり期待しすぎるのは禁物です。何故なら、ある生物のゲノム情報からその生物の形や機能を予測するのは不可能に近いからです。初めて訪問した国で、初めて入ったレストランのメニューやレシピの文章から、その料理の形状や味を想像することが難しいように。
ここで筆者自身のことに少し触れておきたいと思います。以前コラムに書きましたように、筆者は科学者の父を持つ家に生まれました。子供がそれとなく科学に親しみを持つように家庭環境は十分にセットされていたと思います(文献2)。ところが戦中(第2次世界大戦)と戦後を通して父が南方に軍属として出征していたので、その間すっかり自由を満喫し過ぎたようです。海が近かったので、近所の人から魯漕ぎの舟を借りて一人で釣りに行ったり、少年野球にも没頭しました。
12歳で敗戦という未曽有のカルチャーショックを受け、さらには一日にして変節した教員や大人達が全く信じられなくなりました。戦後、父が帰国した後のある日、一寸した諍いで、父の顔を平手打ちしてしまいました。このことに関して両親とはその後話したことはりませんが、この日を境にお互いに子離れ親離れが出来たことだけは確かです。
頼りになるのは自分だけだという事に初めて気付き、学者になろうと決意したのが高校3年生の時でした。筆者は生まれながらの“ものぐさ”ですので、ここ迄の議論が正しいとしますと、学者に適しているはずです。大学では専門書はあまり読まず、専ら気象、天体、物理学等の日本語の解説書や雑誌等を手当たり次第に乱読しました。理解できてもできなくても、最後まで読み切ることに努めました。これは父の教えによるものです(文献2)。
特に理論物理学の成果が、素粒子から宇宙の誕生までの広きに亘って有用であることに感銘を受けました。そして、理論物理学の大発見に机上実験と“閃き”が如何に重要な働きをしているかを知りました。子供の頃の自由な遊びと乱読は、後々の筆者のサイエンスにとって本当に役に立ちました。この過程で筆者の脳にインプットされた種々雑多な記憶が後なって閃きを通して具現化されたものと思います。
一度閃いた後は論理的思考が必要なステージに入ります。幸いにも、筆者の場合には多くの学者や知人のご協力によってこのステージを乗り切ることが出来ました。
机上実験は基本的にお金が掛る作業ではありません。今日ではITの発達により、場所を問わずサイエンスの醍醐味を味わうことが出来ます。読者の皆様、是非この機会に擬態の解明に挑戦してみてください。皆様の知識、経験はそれぞれにユニークであり閃きの宝庫です。得てして、専門家ほど常識や知識が邪魔をして閃きが苦手になるものです。皆様の閃きに期待しています。そして、『机上の空論』ではなく『机上の正論』(最近、NHKテレビで聴いた言葉)を是非体験してください。
2025年10月16日
古澤 満