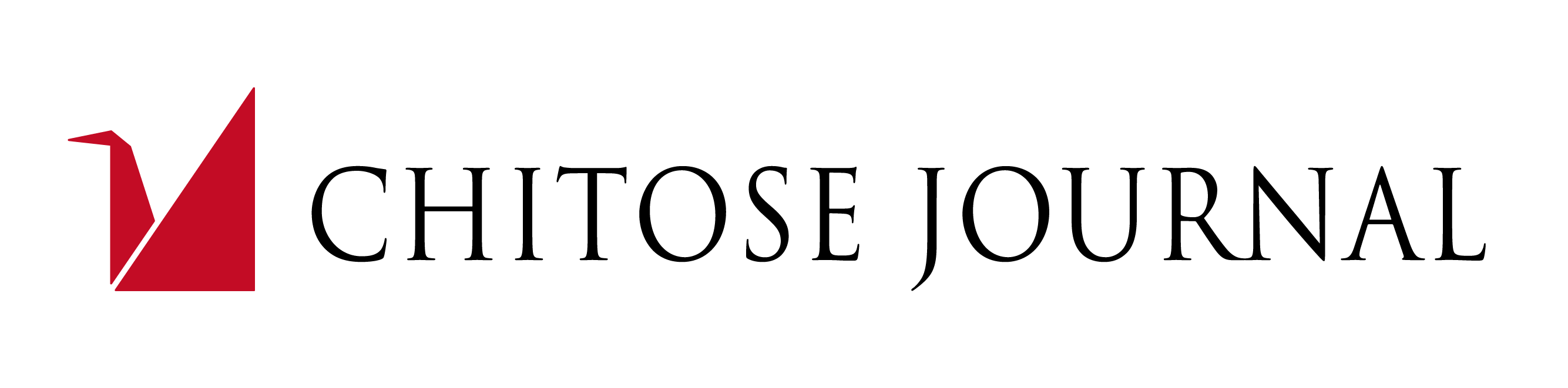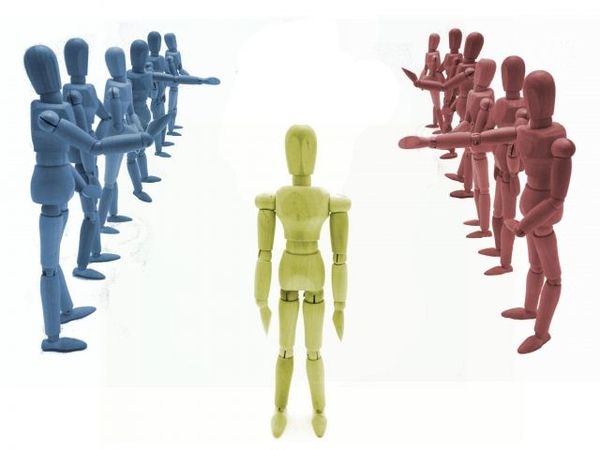
[初出:JBPress]
大企業の安全神話が崩れ、ベンチャー企業の存在感が増していく中、ベンチャー業界を取り巻くさまざまな論説が流れている。だが、当のベンチャー企業側は、その現状と行く末をどのように捉えているのだろうか。戦略コンサルタントを経てバイオベンチャーを創業した、ちとせグループCEOの藤田朋宏氏が、ベンチャー企業の視点から日本の置かれた現状を語っていく。(JBpress)
資金調達やIPOは手段の1つに過ぎない
前回(http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/54289)は、「ビジネスプラン」をテーマに下記のことを書きました。
まず、世の多くのビジネスプランコンテストは、有望な技術や人材を有するベンチャー企業のシェアを安く青田買いしたいという経済的動機を持つベンチャーキャピタリスト達の営業努力によって存在しているということ。
したがって、技術を社会にどのように展開するかとか、実際に携わる経営者や従業員たちの幸せのあり方はどうかまで考えたビジネスプランを提出しても、それはベンチャーキャピタルの利益とは関係の無いことなので、ビジネスプランコンテストでは勝てないということ。
そして、それでも、どうしてもその手のビジネスプランコンテストで最優秀賞をとる必要があるときは、ベンチャーキャピタルの利益のみを追求するようなプランを出せば良いけど、私はそういうのは勧めませんということ。
かなりシニカルに書いてしまったのに、予想以上に多くの方から賛同を頂きました。賛同のコメントを読んでいると、やっと日本のベンチャー業界のあり方も成熟してきて、ベンチャー業界そのものが、より良い方向へ変わっていく潮目にあるのかもしれないなぁと感じています。
前回も書きましたが、私は「人の生き様に優劣がないのと同様に、ビジネスプランにも優劣なんかない」という考え方です。
ですので、早期にベンチャーキャピタルの資本を受け入れて資金量をテコに市場を制圧するという戦略も、生き様の1つだとは思っています。実際に、私も過去にこの戦略を選んだこともありましたし、今後もあるとは思います。
しかし、ベンチャーキャピタリスト諸氏がせっせと布教しているような、ベンチャー企業にとってこの生き様のみが正解だと断定するような考え方には、私は大きな違和感があります。
(また、資金量をテコにして市場を制圧するのを是とする割には、日本のベンチャーキャピタルが供出できる資金量が米国や中国に比べると桁が2つ小さく、圧倒的な物量で市場を先に制圧するような戦略を遂行するためには、日本のベンチャーキャピタルは箸にも棒にもかからない存在であるという議論は、また別の機会にします。)
つまり、有名なベンチャーキャピタルから資金を調達し、IPOを目指すというのは、ベンチャー起業が掲げたビジョンを実現するための手段の1つでしかないはずなのに、ベンチャーキャピタルからの資金調達やIPOをすること自体、そして時価総額が1000億円を超えること自体がベンチャー企業経営の目的のように語られがちな現在の日本のベンチャー業界のあり方に、私は大きな違和感を持っているのです。
ベンチャーを巡る不毛なサイクル
人はなぜ、ベンチャー企業を立ち上げるのでしょうか。誰かがベンチャー企業を立ち上げてしまったことが原因で、多くの人の人生を不幸と混沌の中心に巻き込む可能性が大いにあるのにもかかわらず。
それでもわざわざベンチャー企業を立ち上げる決断をする理由は、今よりも豊かな世界を産み出すための方法として、他の方法よりもベンチャー企業を立ち上げるという手段が有効だと思ったからだと思うのです。
もちろん、豊かな世界よりも、豊かな自分を産み出す方法であるという視点を優先する人も少なくないですが、それはそれで健全な動機だと思います。
社会を豊かにしたいのか、自分の懐を豊かにしたいのかなど、ベンチャー企業を立ち上げる動機にはいろいろありますが、少なくとも間違いなく自信を持って言えるのは「誰かの資金運用の中抜き仲介業」でしかないベンチャーキャピタリストを儲けさせたり、彼らに業界の権力者として君臨させるための糧(かて)、いや餌(えさ)になることが目的で、ベンチャー企業を立ち上げる人なんて1人もいないはずだということです。
(ここまで意識的に「起業」という言葉を使わず、ここからは「起業」という言葉を混ぜ始めている理由は、徐々に分かる仕組みになっています。)
では、なぜベンチャーキャピタリストの餌になりたくて「起業」する人なんて1人もいないはずにもかかわらず、多くの人が喜んで自ら進んで、ベンチャーキャピタリストの餌となる人生を選ぶのでしょうか。
ここ十数年間、国を挙げて「起業だ起業だ」と騒げば騒ぐほど、目に見えて儲かるのはベンチャーキャピタルばかりで、事業的にも個人的にも経済に四苦八苦するベンチャー企業を立ち上げる人の数が増えるだけという傾向があります。
そうであるにもかかわらず、日本はこの現象を周期的に繰り返してしまうのはなぜなのでしょうか。日本は、あと何回この不毛なサイクルを繰り返せば、本当の意味で産業の構築に資するような、健全なベンチャーエコシステムを生むことができるのでしょうか。
前回は、その具体的な理由の1つとして、「ベンチャー企業を立ち上げようと考えている人に、業界の正しい情報が提供されない仕組みになっている」ことだと書きました。他にも、よく言われるように人材の流動性の議論や、株式市場の未熟さなどさまざまな原因があると思いますが、間接的ではあるけれど、より本質的で根深い理由が有るような気がしています。
今回は、その「間接的だけど無視できない理由」について考えてみたいと思っています。
高度にシステム化された入試や就活
ベンチャー業界に身を置いて15年が経ちますが、この15年でいわゆる「良い学歴」や「良い職歴」を持つ人がベンチャー業界に飛び込んでくる率が上がっているように感じます。
他の国は知りませんが、日本において学歴とは「誰かが決めた指標に寄り添い、他者が設定した指標に自分を合わせるのが得意かどうか」を測った結果であると私は感じています。
暗記中心の筆記テストの割合を減らし、考え方を評価する論文や面接での採点を重視すると方針を変えても、「公平な評価」が正解であることを前提とする以上は、誰かが論文や面接を評価するための「指標」を設定せざるを得ません。その結果、誰かが決めた指標に自分を合わせるのが得意な人が、勝ち残る仕組みになっていること自体には何も変わりはないと思うのです。
むしろ暗記中心のテストだったら、誰かが決めた指標ではなく教養とか知識を試験しているとも言えたのに、面接や論文を重視したらそれは考え方を誰かが決めた指標に合わせるという一種の人格統制になりかねない、とひねくれたことを思うのは私だけでしょうか。
学歴だけではありません。現代の日本社会は職歴でさえも「誰かが決めた指標に自分を合わせるのが得意かどうか」を示している気がします。
45歳の私よりも年上の世代の就職活動時の武勇伝を聞くと、日本を代表する大企業の多くでさえ、今の若者からしたら信じられないような「テキトーな採用」と「ノリで就職」で会社を決める社会だったと感じます。
一方で、現在の高度にシステム化された就職活動においては、大きく立派な会社ほど採用のシステムがしっかり作り込まれているため、結局のところ「誰かが決めた指標に合わせるのが得意かどうか」を測っているに過ぎないということが多いのではないでしょうか。
(「人材のダイバーシティを担保するための指標」ってその存在に論理的な矛盾があるのに、不思議だなぁと思うのも私だけでしょうか。人のあり方に何らかの指標を設定したらその次元でしか人材を見てないことになるわけで。)
「起業」は本当の「目的」か?
こうした現代社会の「高度にシステム化された入試や就活」を先頭でくぐり抜けてきた人材たちに、「起業」という新たなチャレンジを示すことで起業を促すのが、現在の日本のベンチャー業界のやり方です。
例として、某有名大を卒業し現在は某有名商社に勤める29歳のA君が、起業を考えているとしましょう。
A君は大学入試の分析が得意な先生から「某有名大はこういう問題がよく出るよ」というタイプの教育を受け、就職活動においても「商社A社では、こういう質問にはこういう答えをすることを求められている。商社B社はちょっと違ってこうだ」などというシューカツ仲間との情報交換などに努力することで、誰もが羨むキャリアを作ってきました。
真面目で、何事にも熱心で、素直な好青年であるA君は、自分の価値観を他人の価値観に合わせることがキャリアを前に進める方法になってきた、なんてことは意識したこともなく生きてきたことでしょう。
むしろ、誰かが設定した指標に自分を合わせるたびに、周りの多くの人から褒められ、多くの人の笑顔を見られる経験をしてきたA君に、私のようなへんてこなキャリアのおじさんが、「他人の指標に自分を合わせるのではなく、自分の指標を作る努力をしないと『起業』はできても『経営』はできないと思うよ」と言ったところで、なんだか変なことを言うおじさんだなと避けられるだけで、本質的に何を指摘されているのかも、なかなか分からないはずです。
そんなキャリアの上で欲しい称号を着実に得てきたA君にとっては、「起業」という新たなチャレンジの存在を目の前に提示された時に、なんの違和感もなく、まず誰かに認めてもらうための「指標」を探してしまうのは、子供の時からの性(さが)なので仕方のないことです。
こんな世界感に生きるA君にとっては、「有名なベンチャーキャピタルからの資金調達」や「マザーズでの上場」が、なんの違和感もなく起業の「目的」になってしまうことは仕方のないことなのです。
そんな、頭の中が「起業、資金調達、そして上場」で一杯になっているAくんに「いやいや、そもそもA君は何を実現するために起業という手段を選ぶの?」と言ってくれる人はあまりいません。
むしろ「そんなリスクの大きいことは反対だ」と親御さんや周りの大人が言えば言うほど、誰かが決めた指標に寄り添いやすい素直なA君は「起業、資金調達、そして上場」こそが現在の価値観における正義であって、大人たちの意見は古くさい意見だと思い込む方向に進むはずです。
繰り返しますが、私は「起業、資金調達、そして上場」が悪いと言っているわけではありません。私は「ベンチャー起業を立ち上げることも、ベンチャーキャピタルや市場からの資金調達も、全て何かを実現させるための手段ではあって、仕事の目的でも、人生の目的でもないだろ? そこは整理しなくて良いのか?」と言いたいのです。
物心ついた時から、学問そのものに興味があって勉強をするのではなく、○○高校や○○大学の肩書を得るために勉強してきたA君です。実際に、そうすることで周りの多くの人の幸せな笑顔を見ることもできました。そんなA君に「起業、資金調達、そして上場は、ただの手段であって目的ではないよね?」と、どんなに言葉を変えて説明しても、場合によってはA君の半生を否定しているように聞こえてしまうため、本当の意味でこちらが何を言っているのかを理解してもらうのはかなり難しいのです。
何年経っても日本に健全なベンチャー業界を育てるエコシステムが生まれない最大の理由は、この物心ついたときから20代前半までに徹底的に刷り込まれる「他人の指標に合わせて自分を変えれば、自分も周りの人も幸せになれる」という価値観が、ねっとりと日本の社会に浸透している点にあると私は考えています。
いつも心に「うるさいボケっ。」
ベンチャー企業を経営してくると、ありとあらゆる立場のステークホルダーが、良かれと思っていろいろな意見を言ってくれます。
どんな意見であっても耳を傾けるべきだと私は思っていますが、一方でステークホルダーたちの人の数だけ存在する生き様や価値観の全てを満たすことを考えていたら、経営なんか成立させられません。経営判断に絶対の正解なんて無いのですから。
社会の中で、吹けば飛ぶようなベンチャー企業の経営とは、大勢の強面のステークホルダーに囲まれて、ショッピングセンターの裏の駐車場に連れて行かれて「ほらジャンプしてみろ」「まだ金持っているじゃないか」と脅され続けるようなものです。
そんな修羅の道でなんとか十数年生き延びてきた私の経験からつくづく思うのは、基本的にステークホルダーというものは、当人が個人的に得をする時に褒めてくれるということです。
物事にはWin−Winで共に成長できることも少なくありませんが、きちんと工夫しないとゼロサムゲームのことの方が多いのが実際です。
つまり、誰かに褒められているときは、相手だけ気づいていて、自分は気づいていない理由で、自分の会社に損をさせていることが多いのです。
しかし、他人の指標に合わせ、他人から褒められることで成功してきたA君のようなタイプの人が社長になった結果、当人のポテンシャルも、全ての条件もどんなに良い状況にあったとしても、多くの人の意見を取り入れようとするがあまり、自分の考えを貫くことができず、経営状態が一定のラインまでたどり着く前に折れてしまう例を私はこの15年間でたくさん見てきました。
高度にシステム化された日本の社会で優等生だった人が、ベンチャー企業を立ち上げようと思ったら、「誰かに褒めてもらうことを求めない」と固く心に誓うことは、必須のように思います。
A君に「手段と目的を取り違えるな」と言うような私も、高度にシステム化された日本社会における優等生の1人でした。そんな私にとって、誰が相手であっても相手の指標に自分を合わせず、「そんなことは何回も考えた上で言ってんだよボケっ」と言い放てるような精神状態に自分を置き続けることは、常に意識して努力を続けて来たことですし、実は今でも常にしている努力です。
そんな努力を、私はいつも心に「うるさいボケっ。」を持ち続ける努力とこっそり呼んでいます。
今回のタイトルは、「起業するなら『誰かに褒めてもらおう』と思うな!」となかなか挑戦的なタイトルにしてしまいましたが、「誰にも褒められない」とか「常に自分の意志を貫く」とかちょっと重ためなことを意識すると、それはそれで人の言うことを聞かない重たい人になってしまいそうです。
ですので、ステークホルダー全員の言うことは、聞ける限り全部聞いた上で、「うるさいボケっ。」って心の中で言える精神状態でいられるように努力し続けるくらいの感じが、ベンチャー企業の経営者のバランス的にちょうど良いような気がしています。