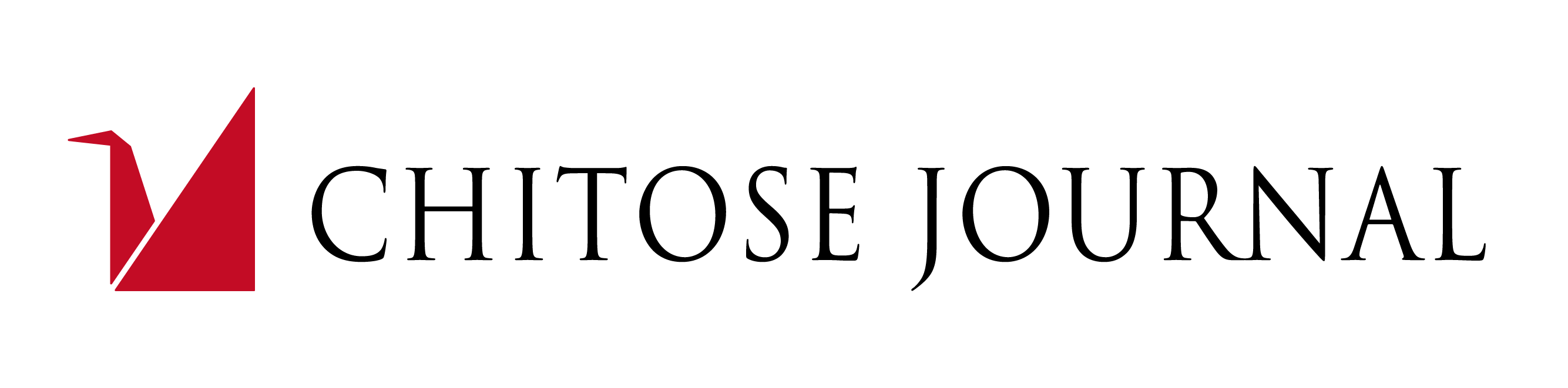中立説(分子進化の中立説)は、木村資生博士が提唱した我が国発の進化理論です。自然淘汰を軸にしたダーウィニズム一辺倒の世界の研究の流れに反旗を翻し、当時誰もが発想しなかった中立突然変異の進化への貢献を数理的に証明したのは本当に痛快でした。著者は京都大学の岡田節人博士のご紹介で、学会の会場で木村博士とご挨拶を交わしたことはありますが、博士と時間をかけて進化について議論したことはありません。
分子進化の中立説の強い支えとなった事実の一つは遺伝暗号の冗長性です。アミノ酸は3つの塩基の組み合わせ(コドン)で規定されます。しかし、例えば20種の内8種のアミノ酸では4種類の異なったコドンで同一アミノ酸が規定される、コドンの重複が見られます。これらの重複コドンでは、2番目や3番目の塩基が変異してもコードするアミノ酸は変わらない場合があります。つまり、塩基レベルでの変異は表現型に表れないので、これらの変異は選択圧に対して理屈上は中立と見做されます。仮に塩基置換のためにアミノ酸の種類が変わった場合でも、タンパク質としての活性にはほとんど影響がなく、淘汰の対象にならないケースも多々あるでしょう。
このように、中立変異は染色体DNAのいろいろな場所でいくらでも起こり得るものです。なお、同義語置換変異は非同義語置換変異と比べて細胞へのストレスが僅かに少ないだけであり、文字通り中立であるとは限らないという近年の報告を踏まえると、単純なコドン表の定義だけでなく、細胞の種類や状態により中立的な変異の種類は変化する可能性があります(文献1)。
木村博士は『中立説の下ではもっとも幸運なものが生き残る』と表現されています。中立変異が生き残る条件として、主に遺伝的浮動(中立変異は野生型に比べてもともと優位性がないので、変異遺伝子が次世代に伝わる確率は交配のような偶然によって決まる)や集団のサイズ等に影響されると考えられています。場合よっては、中立変異は自然選択よりも、より効率的に次世代に残ることもあります。
ゲノムの中には未完成の遺伝子(あと数個の塩基変異が加われば新規遺伝子になる、いわゆる偽遺伝子)が散見されますが、これら偽遺伝子は発現していないので淘汰の対象にならないと仮定すると、生き残る確率が高いといえます。将来、子孫の大進化に役立つ“ロイヤル・ストレート・フラッシュ”の候補遺伝子も偽遺伝子の中の一つです。このストーリーは夢物語ですが、決して中立説がダーウィン進化を無視している訳ではありません。
このように、中立説は生体分子の変異という確固たる事実に裏付けされているので、信頼度の高い学説です。主にサンプルは現存生物から得られているので、現存生物の進化状態をよく説明していると思います。しかし反面、進化の重要なイベントである過去に起こったであろう大進化や進化のジャンプのような劇的な変化の説明には今一つ力不足だと感じるのは筆者だけではないしょう。つまり、中立説は進化の一部を説明していますが、進化全体をカバーするほど強力な理論ではないと言う印象を持っています。
一方、第57回コラムでも指摘しましたように、中立説を含めてダーウィニズムを基盤とする現在の集団遺伝学では変異は集団のすべての遺伝子にほぼ一定の確率で生じるものと仮定しています(文献2)。これに対し、我々が主張する不均衡進化理論では、DNAが複製して生じる2匹の子供の間の変異率の差(FD=fidelity difference)に着目します。すると想像を超えた進化に好都合な条件が現れます(文献2)。
一方、不均衡進化理論は中立説と敵対するどころか、それをサポートする部分を持ち合わせています。主な理由に次の2つを挙げることができます。
1)遺伝子の相互作用を考慮したDNA型遺伝アルゴリズムによるシミュレーションでは、適応度が十分に上昇して安定期に入ると、変異は一定の確率を保ちながら生体に入り続けますが、適応値は殆ど変化しない状態に落ち着きます。この状態を“divergence mode”と呼びましたが、どこか将棋の“千日手”に似ています(文献3)。この状態は適応度の上下に影響しない変異が生じ続けるという点で、中立変異と同等と見做せるでしょう。均衡変異の場合は、変異率の高低に関わらず“evolution mode” から多様化モード(“divergence mode”)に移行してしまいます。一方、不均衡条件では、変異率が高くなり遺伝子間の相互作用が切断される確率が上昇すると、休眠モード(stun mode)の状態をとります。
2)上述しました特殊な偽遺伝子“ロイヤル・ストレート・フラッシュ”は、不均衡変異の場では圧倒的に高い確率で保存されます。何故なら、どちらか一方の子DNAはもう一方の子供より優位に変異率が低いからです。中でも、一方の変異率が0で変異が起こらないときは、ほぼ確実に当該偽遺伝子は集団内に担保され、将来の劇的進化のために出番を待つことになります。また、不均衡変異の特徴として、色々な遺伝型が保持されたまま進化せずに“stun mode”(短期間行動不能に落ち入る状態)に入る事が出来ます(文献3)。
ところで、実験的検証が可能な進化理論は極めて稀ですが、進化の不均衡説は実験検証が可能です。たとえば、特定のレプリコン(DNAの複製単位:染色体は複数のレプリコンよりなり、すべての遺伝子はいずれかのレプリコンに属します。)のFD値を遺伝子操作によって変更させ、環境の制御と組み合わせれば進化の方向性を変えることが可能となるでしょう。著者が幼い頃から夢見た“実験進化”の実現です(文献4)。
不均衡進化理論と中立説は進化研究の上でどのような関係にあるのでしょうか?分子進化の中立説は理論と実験のもとで成立しました。一方、我々が提唱している不均衡進化理論はDNA複製の構造的非対称という分子生物学(構造生物学と呼んでもいいかも知れません)に基づき立脚されたアブダクション(仮説的推論)であり、近年では様々な分子レベルでの実験結果によるサポートを受けています(文献5)。俯瞰しますと、中立説も不均衡進化理論も結局はダーウィン進化と同じ土俵に立っていると思います。上述しましたように、不均衡進化モデルから中立説と同じ状態は導けますが、中立説の理論的枠組みから不均衡進化モデルを演繹することは難しいと筆者は考えています。中立説の立場からの不均衡進化理論に対する評価を是非お伺いしたいと思っています。中立説に対する筆者の理解はまだまだ不十分だと自覚していますので、更なる研鑽を重ね理解を深める必要があると感じています。
2025年11月11日
古澤 満
文献:
- Shen, X., Song, S., Li, C. et al. Synonymous mutations in representative yeast genes are mostly strongly non-neutral Nature 606, 725–731 (2022)
- 不均衡進化理論とネオ・ダーウィニズム[第57回 古澤満コラム]
- Akashi, M., Fujihara, I., Takemura, M. & Furusawa, M. 2-Dimensional genetic algorithm exhibited an essentiality of gene interaction for evolution Journal of Theoretical Biology 538, 111044 (2022).
- 古澤満著「不均衡進化論」(筑摩選書)、筑摩書房
- Furusawa, Mitsuru, Ichiro Fujihara, and Motohiro Akashi. DNA Sequencing Technology Reveals Disparity in Mutagenesis Due to Fidelity Differences between Two Daughter DNAs in Evolution IntechOpen, 1–24 (2024)