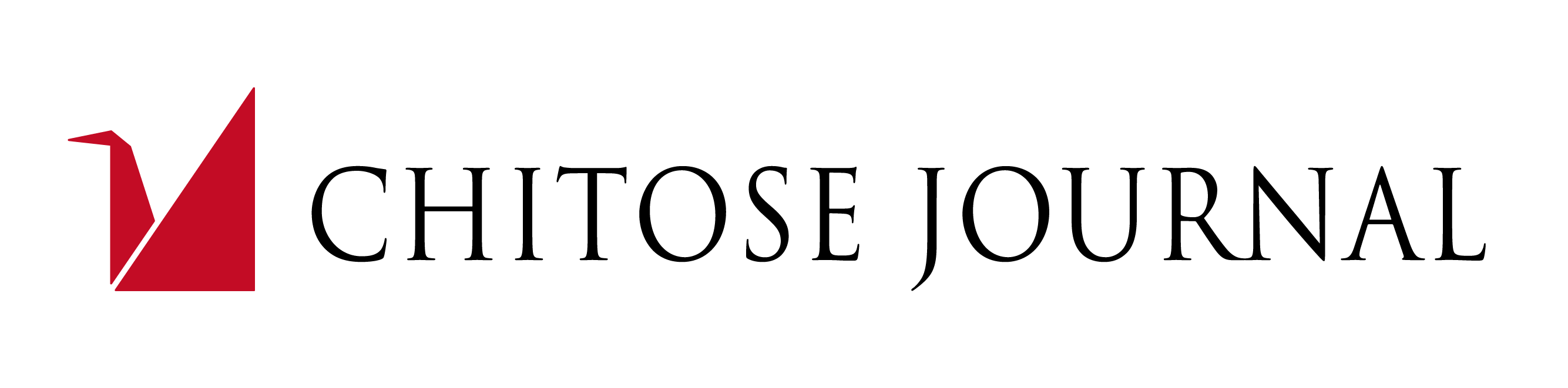潮風がびゅうびゅうと吹きすさぶ、みなとみらいの一画。ガラス張りの建物に入りホッとしたのも束の間、緊張とも期待ともつかない感情で心臓が一段ギアを上げた。この日はMATSURI全体会、一年で一番MATSURIが「祭」になる日だ。
今回のMATSURI全体会は、発足以来初めてパートナー企業のフィールドで行われた。舞台はプラチナパートナーである資生堂の研究拠点、グローバルイノベーションセンター。ここに対面・オンライン合わせて約300名のMATSURIパートナーが集結した。
全体会は、MATSURIの活動報告を中心に、共創事例の発表や課題の共有、そして協業の呼びかけが交差する場となった。この日、壇上に立った多彩な語り手たちの講演をダイジェストで報告する。
目次
ちとせグループ代表 藤田朋宏

最初にマイクを握ったのは、ちとせグループ代表 藤田朋宏。「藻類産業を構築する」と銘打ってきたMATSURIが、今年からその対象を「バイオエコノミー全体」へと拡大したことを改めて宣言した。藻類にとどまらず、微生物の力を活かした発酵など多様な手法を通じて、社会全体を石油基点からバイオ基点へとシフトさせていく。そしてそのビジョンの土台となる、新しいMATSURIの7つの価値観を示した。
Microorganisms(微生物)
Agri-Engineering(農学)
Transparency & Trust(透明性と信頼)
Sustainability(持続性)
Unused-resources(未利用資源)
Radiant power(太陽エネルギー)
Industrial scale(産業規模)
藤田は「新たにバイオ産業が生まれるのではなく、既存のすべての産業がバイオ化する」と述べ、そのとき起こる社会の変容を数十年スパンで展望した。かつてデジタルが社会の隅々に浸透したように、これからはバイオが社会の標準装備となり、富のあり方さえも変えていく、と。
社会はこれから大きく変わる。原料のバイオ化、AIの発展、国際情勢、その波を乗りこなすために必要なのは、個社では困難な挑戦を仲間で分担し、みんなで儲かる事例として成果を積み上げていくことだ。バリューチェーンの上から下までMATSURI一丸となり、次の世界標準に向き合っていこうと締めくくった。
福島国際研究教育機構 土壌ホメオスタシス研究ユニット ユニットリーダー 藤井一至先生

藻類から出発したMATSURIは、微生物全般を含む「バイオエコノミー」へと対象を広げた。その延長線上にある「土」もまた、無数の微生物がつくりあげた存在だ。そうした背景から今回は、『土と生命の46億年史』の著者で、土壌学の第一人者でもある藤井一至先生に特別講演をいただいた。
土。ヨコ、タテ、ヨコ、の画数わずか3つの漢字。最も身近で簡単な言葉のひとつだが、私たちは土が何なのか知っているのだろうか。それどころか、そんなことすら疑問に思ったこともないのでは?藤井先生は、何億年という時の流れと、大陸間を自由自在に行き来しながら、土のスペクタクルを語ってくれた。
まず、それが「単なる物質ではない」ということに驚かされる。それは、悠久の時を経て、石の風化と微生物たちの営みが折り重なってできた「システム」なのだ。そして同時に、「文化」でもあるという。我々の食の95%は土に依存し、さらにアルミや半導体などといったスマートフォンの部品すら元を辿れば土から出来ている。土は、人と社会を支える数え切れない価値を生み出してきた。
土をめぐる地球規模の課題は様々あるという。だが人類は時にそれに対して消耗戦になりがちだそうだ。だが藤井先生は強調する。「完璧な土もなければ、必勝法もない。むしろ、それこそが土の本質であり、魅力だ」。そして最後にこう結んだ。「Enjoy Science、ではなく、Enjoy Your Science! 自分の研究を自分自身が楽しむことが大切」と。
先生の言葉は、一人ひとりの背中を押す。各自の“Your Science”の積み重ねが、MATSURIという場で結びつき、バリューチェーンをつなげていく。その先にこそ、私たちの目指す産業の地平が開けるのだと信じている。
株式会社資生堂 執行役 エグゼクティブオフィサー チーフマーケティング&イノベーションオフィサー 岡部義昭様

岡部氏の講演は、“BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD(美の力でよりよい世界を)” という資生堂の企業使命を掲げた映像から始まった。美には人の心を豊かにし、生きる喜びやしあわせをもたらす力がある。このムービーを受け、岡部氏は資生堂の社名の由来である「至哉坤元 万物資生(大地の徳はなんとすばらしいものであろうか、すべてのものはここから生まれる)」と、ちとせのビジョン「生き物たちの力と共に 千年先までもっと豊かに」は、根底で調和していると示した。
講演のハイライトとして披露されたのが、藻類を活用したスキンケア化粧品プロトタイプ「美の玉」だ。大阪・関西万博の日本館「『藻』のもの by MATSURI」で展示され、多くの来場者を驚かせているその製品を、壇上で実演を交えながら紹介した。 資生堂は、115社というパートナーの中でもいち早くプロトタイプを具体化し、産業構築のフロントを切り開いている。これまで積み重ねた研究と、MATSURIの志が社会に見えるかたちへと結実した瞬間を会場は目にしたのだ。
大阪・関西万博 日本館展示紹介 Senior BioEngineer 切江志龍 Senior Manager 今野夏穂

続いて、万博担当の切江と筆者・今野から大阪・関西万博日本館の近況を共有した。日本館のコンセプトは循環、そしてテーマの一つが藻類だ。今野からは、日本館の藻類関連展示についてダイジェストで紹介し、改めて「『藻』のもの by MATSURI」の協賛各社に謝意を述べた。
また懇親会会場と中継をつなぎ、設営中の展示ブースで切江が「『藻』のもの by MATSURI」の実寸大パネルを紹介した。日本館をすでに訪れた方も、まだ足を運べていない方も、資生堂グローバルイノベーションセンターにやってきた「ミニ・日本館」を楽しみ、懇親会でも目玉のひとつとなっていた。
万博会期中、メディアやSNS上で「藻ってすごい」という評判を数え切れないほど目にした。MATSURIを超えて、万博会場も超えて、藻の魅力がどんどん外に広がっていることが何より嬉しい。藻類をはじめとするバイオテクノロジーの勢いが世界中へ波及しつつある。その手応えを、会場全体で共有できた時間だった。
万博の取り組みはこちら:https://chitose-bio.com/jp/expo2025/
マルハニチロ株式会社 品質保証部品質保証統括課 品質保証チーム課長代理 國永史生様

創業から145年、マルハニチロは、海のタンパク質を中心に世界中に届けてきた。同社は「タンパク質クライシス」を見据え、供給の不確実性に揺らがないもう一つの柱を打ち立てようとしている。微細藻類を活用した高タンパク食品の開発はその象徴だ。
日本館での配布に向けて、短期間で開発を実現した「藻類味噌汁~スピルリナ~」は、その意思表示でもある。常温保存・大量提供・ごみを出さない配布形態、日本館ならではの制約を一つずつ解消しながら、スピルリナの鮮やかな緑と味噌のうまみが調和する一杯に仕上げた。来場者からの評判も上々だ。「猛暑の中、万博から帰ってきて歩き疲れ、夕食を作る気力もないときに、お湯を注いで味噌汁を飲めば、日本館での思い出がよみがえり、まさに循環を感じる」といった心温まる声もお客様窓口に寄せられているそうだ。
日々の食卓で微細藻類が自然に選ばれる未来へ。「食を通じて人も地球も健康にするソリューションカンパニー」としての挑戦を、MATSURIと共にさらに広げていく覚悟が語られた。なお、同社は2026年3月より社名を Umios(ウミオス) へ改め、新たな一歩を踏み出す。名前が変わっても、進む方向は変わらない。ここからが本番だ。
ちとせグループ Chief BioEngineer 星野孝仁

藻類事業を率いる星野から、100 ha規模の藻類生産施設開所に向けた進捗の方向性と、直面している課題をパートナーに共有した。
100 haは、現行施設の20倍だが、これは単なる掛け算で済まない。マレーシアの屋外での培養、コンタミネーションの管理、CO₂の供給、乾燥・抽出までの後工程、運用体制… 規模が変われば、課題も全く新しいものに姿を変える。
その難しさに正面から挑む星野の口調は淡々としているが、内容は熱い。設備の設計、藻類の乾燥条件、粘性の高い藻類の扱い、生産の自動化… 課題は山ほどある。しかし各社の知見が噛み合えば、道筋が現実味を帯びてくるはずだ。星野から解像度の高い宿題が投げ込まれ、会場の空気が研ぎ澄まされたのを感じた。
課題の数だけ、ビジネスの機会がある。MATSURIは、その課題をテーブルに上げ、役割を分け合い、利益を分かち合うための場だ。次の一手を打つのは、あなたの会社かもしれない。
懇親会

200名近い参加者で賑わう懇親会は、資生堂・岡部氏の乾杯で幕を開けた。会場内を歩けば、大阪・関西万博 日本館の展示の紹介をはじめ、発酵生産、AI制御技術、ヘルスケア、資源循環、藻類を使った手土産の開発など、藻類産業構築にとどまらず広がる私たちの挑戦が並び、まるで異国のバザールのように右から左から訪れる者の好奇心をくすぐった。3歩進めばこちらから声を掛け、5歩進めば声が掛かる。気づけば豪勢な立食料理も視界の外で、会話の波に飲み込まれていく。
そして周りを見渡せば「ちとせとパートナー企業」という関係だけではなくパートナー企業同士が新たな協業の可能性を探る光景も数多く見られた。藻類の輸送方法から脂肪酸の市場価値、さらにはESG投資の変化と企業の姿勢など、話題は多層に広がる。ここは建前のような共同研究の枠ではなく、そこに関わる者たちが利を求めつながり合う場所なのだと実感した。「MATSURIを軸足に儲けてやろう」という活力こそが、千年先まで走り続けるエネルギーになるのだ。
一人ひとりの意志が産業を動かす
この日、数々の人と言葉を交わし、誰もが自分の持ち場で意志をもち、懸命に手を動かしているのだと実感した。MATSURIという大きな旗を高く掲げながらも、物事を前に進める力はささやかな日々の営みから生まれる。藤井先生の “Enjoy Your Science!” という言葉が頭に浮かぶ。顕微鏡を覗く手元も、マレーシアの炎天下でも、日本館地下の培養部屋でも、提案資料を磨きながら、そして、この原稿を書きながら。
夜の地球に灯りが広がり大陸の輪郭が浮かぶように、一隅を照らす灯りがひとつ、またひとつと増え、つながりあっていく。MATSURIが越えねばならない障壁は大小様々で、まだまだたくさんある。だが、一人ひとりの意志が集まって、産業構造を変えるほどの大きな未来をつくる。ここまで読んでくれたあなたの一灯が、千年先へ続く道を照らすと信じている。