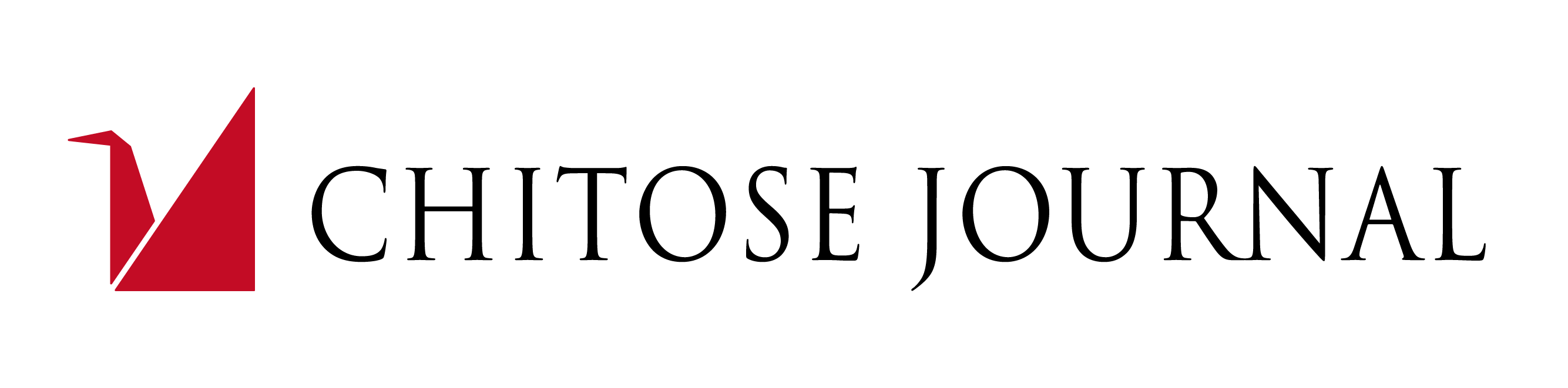前回のコラムで哲学者カントの話が出ましたので、今回は、わが国の大学における哲学教育について私見を述べたいと思います。
遠い昔には科学そのものが存在しませんでしたので、科学と哲学の区別はなく、インテリジェンスに秀でた人であれば誰もが哲学者になり得ました。極端な例として、ルクレティウスが挙げられます。彼は紀元前の共和政ローマ期の詩人ですが、『物の性質について』と題する詩の中で、なんと驚くべきことに自然現象の観察の上に立って素粒子論に通底する物質観を詩っています。物理学者の寺田寅彦氏が上手く訳していますので、興味のある方は是非お読みください(寺田寅彦著『ルクレチュウスと科学』青空文庫)。(この本の存在は弊社の緒方法親氏からの紹介で初めて知りました。)
15~16世紀になると、コペルニクスの地動説に代表される近代科学の黎明期を迎えます。17世紀以降はデカルトやカント、ショーペンハウエルなど、いわゆる哲学者が認識や物質の本質に迫り、のちの科学の発展に大きな影響を与えてきました。一方で、進化論の提唱者であるダーウィンや、遺伝の法則を発見したメンデルは科学者であると同時に哲学者でもありました。このように、もともと哲学と科学は表裏一体の関係にあったのです。蛇足ですが、メンデルの本業はキリスト教の司祭です。
科学や実学が細分化されるにしたがって、当然のことですが哲学はそれらから離れていきました。21世紀の現在では、哲学者とは自己完結型の人間が営む、生産性とは無関係な文科系の一学問だと思い込んでいる人が多いと思います。しかし、哲学とは大学で研究されているような一般人にとって難解な学問だけを指すものではありません。人はそれぞれ独自の信念、信条、スタンスをもって生計を立てていますが、この気構えの部分は一つの哲学であり、人生哲学とも呼ばれています。つまり、哲学を持たない人などいません。人と動物の違う点は、後者の行動には哲学が伴わないことです(勿論、“哲学”の定義によりますが)。
日常生活に役立つ哲学の例を挙げましょう。リン・ユータン(林語堂)は昭和初期に活躍した中華民国の反体制派の文学者で、ノーベル賞候補にもなった人物です。彼の著書『生活の発見』(坂本勝訳/創元社/ 1938年)の一節に、<椅子の足は短い方が楽である >という意味のことが結論的に書かれています。彼の著書は世界中で読まれていますから、椅子の足を切ったり、足の短い椅子を買った人はかなりいるはずです。ここ80年をみても、日本人の足が伸びたにも拘わらず、ホテルのロビーの椅子やソファーの高さは確実に低くなってきているように見えます。たかが椅子の高さと侮ってはいけません。人はどれだけ快適に時間を過ごせることになったでしょう。疲れが取れ、食事が進み、会話が弾むだけでもその効果は計り知れないものがあります。リン・ユータンは優しい表現を使って庶民に溶けこもうとした哲学者です。中学生のころ、父とこの事に関して議論をしたことを想い出します。
さて、本論に入りましょう。大学に哲学科は必要か?という問いにしばしば出会います。答えを先に言いますと、今の形の哲学科は必要ないと思います。
大学で哲学史を学びたい学生に対しては、適切なガイダンスと質問に簡単に答えてあげるだけで十分でしょう。難解な表現を使って過去の大哲学者の解釈論を延々と展開し、それだけで終わってしまうようなカリキュラムは最早必要ないでしょう。歴史は自分で学ぶべきものだと考えます。それが出来ないような学生は、そもそも哲学科に入る資格などないでしょう。哲学の歴史を勉強する学生には、完備された図書と有能な司書がいれば十分です。
では哲学科の先生の役割とは何でしょう?偉大な先人達は、後になって科学のパラダイムシフトを起こすほどの理念や概念を提出しています。私が大学における哲学研究に期待するのは正にこのことです。時代は変わっています。前出のルクレティウスのように、昔は殆ど無の状態から新しい理念や概念の想起が求められました。しかし現在では学問分野を問わず、具体的でしかも整理された形で未解決な大問題が向こうからどんどんやって来る状況にあります。専門家が手をこまねいている難問題の解決策やブレークスルーのヒントを見出すことこそが哲学科の存在意義だと思います。
一生物学者である私が、今思いつく未解決の大問題を列挙してみます。
暗黒物質・暗黒エネルギー、ビックバン以前の宇宙、グラビトンの捕獲(グラビトン:重力を司る素粒子。スピン2、質量0、電荷0、寿命無限大、光速で飛ぶ)、ゲノム情報と生物の形の関係(第39回古澤コラム参照)、擬態、エネルギー問題、人口問題、格差問題、核兵器問題、理想的政治体制。
ここに挙げた例は、専門家である物理学者や生物学者、社会学者の前に立ちはだかる未曾有の大きな壁です。もしかしたら西欧的思考法の限界の到来を示しているのかと疑うほどです。これらの壁をブレークスルーした人は優れた哲学者としても評価されるに違いありません。哲学者には人類が抱えるその時々の大問題の解決策を常に意識していただきたいと思います。何故なら、哲学が科学や実学をリードするのが本来の姿ですから。
以上をまとめますと、哲学科は必ずしも文学部に置く必要はなく、どの学部に所属していても差し支えありません。むしろ文学部は最悪のチョイスかも知れません。場合によっては学科を飛び出して、別の学部に研究室を移すのも一案でしょう。哲学科の先生はもっと積極的に理学や実学と接触すべきだと思います。移転先で日常的に最先端の知識に触れることで触発されることも大いにあり得ることでしょう。文学部の片隅に引っ込んでいないで、外へ出てもっと自由に論戦を張って、持てる実力を十分に発揮していただきと願っています。
大変僭越とは思いながら、日頃から思っていることを書かせていただきました。私は大学の理学部に25年間勤めていた経緯がありますので、この文章を内部批判と受け取っていただいて結構です。
私にとって、哲学はいきざま(生き様)、科学はなりわい(生業)と割り切っています。30年に亘る私たちの進化の研究成果を一言で表現すると、「生命を含む複製系において、バランスの崩壊は創造を生む」となります。これが哲学であるかどうかは読者のご判断にお任せします。
2019年2月10日
古澤 満