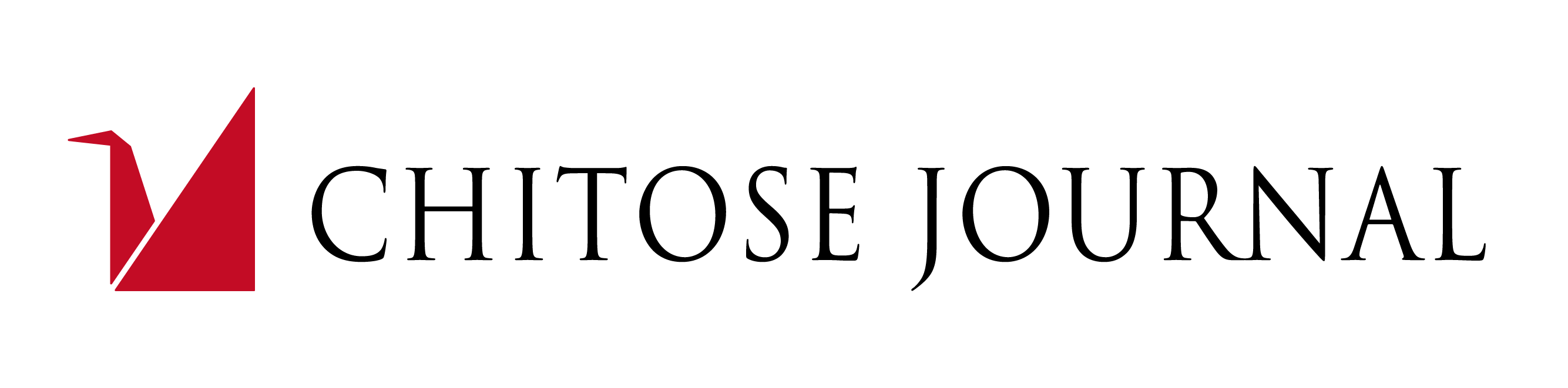藻類と牡蠣の共通点?旨みだろう!
ちとせのターニャです!大崎上島で、東京大学の「共生型新産業創出コロキウム」のフィールドワークを続けましょう〜!
前回記事:ターニャ、津々浦々で藻と出会うVol.1
藻類を飼料として活用すると、魚介の生産量が向上し、持続可能な養殖につながることをご存じでしたか?最近、万博日本館でも注目を集めている微細藻類は、魚粉の代替として期待されており、魚粉の製造に伴う乱獲や生産コストを抑えるポテンシャルがあります。
広島で養殖の現場を訪れるなら、やはり牡蠣の生産地を見学するのが最適でしょう!牡蠣がどのように育てられるかを学びながら、持続可能な養殖の未来を感じられました。
今回はFARM SUZUKIを訪問させていただきました。フランスの養殖技術を学ばれた代表の鈴木様は、質や味にこだわりながら、大崎上島の塩田跡地にある約10万平方の池で牡蠣、車海老、あさりを育てています。

牡蠣の味や健康は、生育する生態環境によって大きく左右されるため、藻類の有無を含む環境の精密な管理が不可欠です。例えば、フナガタ珪藻で育てられた牡蠣のエラがエメラルドグリーンに変わり、最高級の「グリーンオイスター(緑牡蠣)」として高く評価されています。
水中に藻類やプランクトンなどの微生物を与えることで、牡蠣が暮らしやすい豊かな生態系が保たれ、健康的に育ちます。そうして育った牡蠣は、味わいも一層美味しくなるのだと学びました。
一方、オープンポンドの養殖なので、空気との接触でコンタミネーションも起こることがあり、毎年一回池の水を全て抜いて、そこを綺麗にし、耕してから生態を整えるために微生物を散布するという、大きく汗をかく仕事もされています。
受講者たちは、藻類由来の燃料など将来的な可能性だけでなく、現在進行中の藻類の実用例についても学ぶことができ、非常に貴重な機会となりました。
微細藻類の海上培養って何?
大崎上島フィールドワークの最終日になりました。こんなに小さい島なのに藻類に関わる活動が著しく多いと感じました。12月10日に訪れた広島商船高等専門学校では、大沼みお教授が海上藻類培養や藻類バイオ燃料の生産効率向上について研究をされています。
海上藻類培養は、培養液が含まれる楕円体、または直方体の培養容器を海上に浮かべ藻類を育てる手法です。この方法は、海上に降り注ぐ日光を活用できるだけでなく、波の動きを攪拌する力として活用します!びっくりするでしょう〜

ド文系の私にはよくわからない、複雑な装置の設計や計算が詳しく以下の記事で公開されているので、ご興味があればぜひ見てください。
微細藻類の海上培養モデル-原理と設計
大沼先生の講義および今回のフィールドワークで得た知識を踏まえて、微細藻類の生産に伴う課題について、お弁当を食べながら、参加者とともに活発な議論が行われました。「こうしたらより効率的にできるでしょう」「〇〇は問題にならないのか?」さまざまな面からの質問に対して、丁寧に答えてくださった大沼先生には大変ありがたく感じました!
最後に、広島商船高等専門学校の大沼先生のラボを訪問し、藻類が入っている培養タンクや窓の隣に並んでいる植木鉢を見た私は、新しい世代にインスピレーションを与える大沼先生のお仕事の重要さを肌で感じられました。
昼食後、帰路に就く時間になりました。瀬戸内海の紅葉に魅了された参加者は広島でお世話になった方々にお別れの挨拶をしました。
帰りのフライトで、私は眠りにつきました。藻類燃料を積んだ飛行機が、緑色の飛行機雲を残しながら大空を駆けていく、そんな光景がまぶたの裏に広がっていました。

Vol.2にて佐賀フィールドワークの冒険についてまもなく配信します!