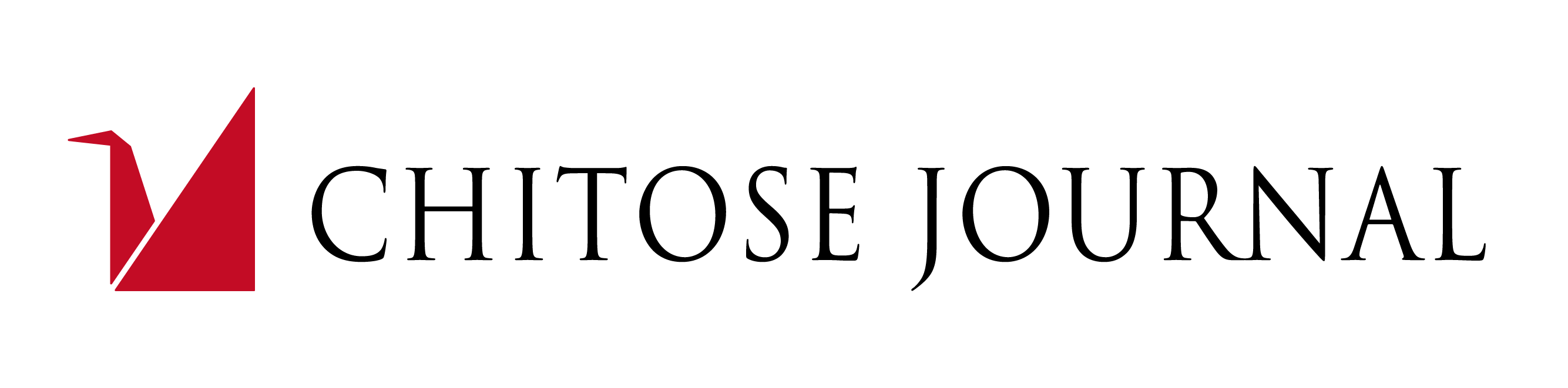「藻」と聞いて、何を思い浮かべますか?池に漂う緑色の物体、あるいは昆布やワカメといったお馴染みの海藻?
今、そんな藻類(そうるい)が、未来の暮らしを支える素材として注目されています。2025年大阪・関西万博、日本館では藻類がテーマのひとつ。そして、ちとせグループが主導するバイオを軸にした産業づくりを進める共創プロジェクト「MATSURI」は、日本館ファクトリーエリアで「『藻』のもの by MATSURI」をプロデュースしました。このショーウィンドウでは、藻類を素材にしたアパレル、化粧品、食品、塗料など、さまざまな「藻の物」が一堂に並びます。

ショーウィンドウの右下に、どっしりと鎮座する精巧なモデルシップがあります。これは、実在する貨物船「KAMSARMAX(カムサマックス)」をモデルにしたもの。船の設計・建造を手がけるのは、日本が世界に誇る広島県福山市の造船会社、常石造船です。そしてこのKAMSARMAXを日本館での展示に導いたのは、船舶の貸渡や運航管理などグローバルな海運ビジネスを展開する富洋海運。
今回は、KAMSARMAXの設計を担う常石造船の関さんと、この展示の立役者、富洋海運グループのMers Line代表・久保さんに、海を駆ける巨大な船の裏側とその設計に込められた美学について語っていただきました。
同日、取材に同席いただいた海事プレス日下部記者による記事も公開中です。専門メディアならではの視点もぜひご覧ください。
[海事プレス] 柔軟性が脱炭素移行期のカギ【対談】マーズライン・久保氏×常石造船・関氏

今回お話を伺った方
久保 勇介さん(Mers Line Pte. Ltd. 代表)
関 和隆さん(常石造船 設計本部 商品企画部 部長)

用語解説
■KAMSARMAX
西アフリカ・ギニアにある「カムサール港」に入港できる、常石造船が独自開発したばら積み貨物船。全長は229m、最大積載量82,000トン(ごはん15億杯分=1クラス30人が毎日3食食べ続けて約5万年相当!)で、世界中の穀物や鉄鉱石などを運ぶ。海運業界の市場動向を示す指標であるバルチック海運指数の1つとなっている。
■デュアルフューエル(二元燃料)
エンジンが2種類の燃料に対応している仕組み。1種類の燃料ではなく「重油とメタノール」など、状況に応じて燃料を切り替えることができる。これにより、より環境負荷の低い燃料を選択できるようになり、脱炭素化に向けた移行をスムーズに進める技術として注目されている。日本館で展示されているKAMSARMAXの模型は、この藻類由来の船舶燃料で走る、デュアルフューエルに対応した最新船型をモデルにしている。
日本館には、日本で作った世界一を
―― まずは久保さん、この船を万博日本館に置きたいと思った理由を教えてください。
久保さん(Mers Line 代表):
万博という機会、しかも日本館に展示するんだったら、やっぱり世界一と胸を張れるものを置きたいじゃないですか。日本の造船技術って実は世界トップクラスで、色々な「世界一」がある中で、真っ先に思い浮かんだのが常石造船の「KAMSARMAX」でした。
2010年頃、世界のばら積み貨物の運賃指標であるバルチック海運指数中で、この船が標準船型として使われることになったときの驚きは、今でも鮮明に覚えています。「標準船型に選ばれる」というのは、その船の設計力・普及率・性能が国際的に認められたという証です。つまり世界の市場分析や投資判断において、この船の運賃動向が重視されるようになるわけです。シビれましたね!
やはり日本館には、日本で作っている世界一のものを置きたい。今回これが叶って、ひとつ誇れる仕事ができたなと、常石造船さんには心から感謝しています。

――関さんの業務は「船舶の設計」と伺っていますが、あれだけ大きなものの設計となると、具体的にどういったところを担当されているんですか?
関さん(常石造船 設計本部 商品企画部 部長):
私が担当しているのは設計工程の中でも一番最初の開発段階にあたります。「次のKAMSARMAXをどんな船にするか」というコンセプトづくりから始まり、船の長さや喫水(水中に沈んでいる部分の深さ)、積載量、燃費性能などの大枠を定めていきます。
もちろんベースには先人たちが作った理論や設計がありますが、よりよい性能を目指して改良を重ねるのが私たちの仕事です。例えば、今回モデルシップの型になった最新型のKAMSARMAXは特に空気抵抗を受けにくい形状になっていて、これで全体として数%は燃費が変わってきます。
―― デザインやコンセプトといった感覚的な部分と数学的な頭の使い方と、どちらの頭もフル活用しそうなお仕事ですね!ちなみに子供の頃、得意だった科目は何ですか?やっぱり数学ですか?
関さん(常石造船 設計本部 商品企画部 部長):
どうでしょう(笑)図工は好きでしたね。

「船の価値」を決めるもの
――「船の価値」を決める要素は色々あるかと思いますが、やっぱり燃費はその中でも大きいのでしょうか。
久保さん(Mers Line 代表):
大きいです。船って長いこと走るので、数%の差でも積み重なれば非常に大きな違いになります。実際、約10年前の船型と最新の船型では、3割ほどの差ができている。同じものを運ぶのに、使う燃料が3割も減るというのは、莫大なコストインパクトがあります。
それと、どんな港にも入れるフレキシビリティもとても重要です。同じ積載量を運ぶとして、横幅を広げると喫水は浅くなり、入れる港の数は増えますが、通れる水路は減ってしまいます。反対に横幅を狭くすると通れる水路は増えますが、喫水が深くなることで入港できる港が限られてしまいます。
KAMSARMAXは、そうした制約の中でギリギリのバランスを突き詰めた船型です。だからこそ、世界中の港に対応できる。KAMSAMAXってデザインもかっこいいのですが、実用面でも非常に高く評価されています。
関さん(常石造船 設計本部 商品企画部 部長):
外観のかっこよさに関していえば、燃費性能を追求した結果の機能美と言えるかもしれません。例えば、高い波でも抵抗が少なくなる船首部分の曲線、直方体ではなく角を落として風の抵抗を減らした居住区の形状、空気抵抗や水の抵抗をできる限りいなす流線形のライン。どれも機能面で意味があります。常石の船は「性能は良いけど、かっこ悪い」ではなく、「性能も良いし、かっこいい」と言われたい。
久保さん(Mers Line 代表):
全てが緻密に計算されているんでしょうね。たまらないです!

関さん(常石造船 設計本部 商品企画部 部長):
そういっていただけて嬉しいです。KAMSARMAXは、そんな機能性だけではなく、船員たちが暮らす居住区のインテリアにもこだわっています。通常の船よりも天井高を20cmほど高くし、木製家具や間接照明を取り入れるなど。それにエンジンの振動をできるだけ減らして、長い航海をできるだけ快適に過ごしてもらえるように作っています。
久保さん(Mers Line 代表):
船員さんの過ごしやすさって、実はとても大事なんですよ。いい船にはいい船員さんが乗るので、きちんとメンテナンスして長く乗ってくれます。そうすると運航効率が上がりますし、セカンドバリュー(中古船としての価値)も上がります。ここは船の資産価値にも関わる重要なポイントです。

0.01 mmの藻が、229mの鉄を動かす?
―― もともと船は重油で走っていますよね。そこから、デュアルフューエル(二元燃料)で走れる船が登場し「重油×水素」や「重油×メタノール」といった組み合わせも出てきています。そうしたなかで「藻」が入り込む余地ってあるのでしょうか?
久保さん(Mers Line 代表):
常石造船は、これまでに重油だけでなく、LNG(液化天然ガス)や水素、メタノールを燃料とする船も手がけていますよね。藻によっては石油と似た油を出す種類もあるので、技術的にはさまざまな燃料をつくることが可能だと聞いています。ただし、藻を船舶燃料として使うには、コストと供給量という大きな課題があります。いくら燃料ができても、使いたいタイミングで安定して供給できないと、海運では使えませんから。
―― そこはまさに、私たちが挑戦している課題です。ちとせでは、2018年からマレーシアで1,000 ㎡の藻類生産施設を稼働させていて、現在は5 ha規模の施設が稼働しています。さらに100 haへの規模拡大の準備中で、2030年頃には2,000 haまで広げる計画があります。もちろんそのあともさらなる拡大を目指しています。世界中に今あるトウモロコシ畑と同じ広さの「藻畑」を作ったら、人類が必要とする油の半分の量をまかなうことができると言われているんです。
ちなみに、「石油と似た油を出す種」というのは、ちとせでも生産しているボツリオコッカスという藻で、これがとてもよく燃えるんです。何年か前にその藻を乾燥させて、バーベキューの燃料にしたこともあるんですよ。あまりに燃えすぎて、お肉は黒焦げになってしまったようですが(笑)

久保さん(Mers Line 代表):
しかも藻って、ただ油をつくるだけじゃないんです。その搾りかすから食料にもなり得る成分が得られる。先ほど出たボツリオコッカスという藻は、現時点では人間の食用には認められていません。でも、家畜などの飼料としては十分に活用できる可能性があります。その他にも、スピルリナやクロレラなど、食品として高い栄養価が認められている藻類種もあります。将来的には、藻が穀物に代わるもう一枚のカードになるんじゃないかって、そんな期待もしているんです。
油を搾って、その搾りかすは食料に。こうして余すことなく使える点も、藻という資源の面白さであり、可能性です。そしてちとせさんが率いる「MATSURI」がやっているのは、まさにその可能性を現実の産業に接続していく壮大なプロジェクト。そこに共鳴する製造業や、幅広い業種の方々が技術や知恵を持ち寄って、藻から新たな製品の開発に取り組んでいます。そこに我々、富洋海運も参加しているんです。
「2050年カーボンニュートラル」は、実はすぐそこまで
―― ところで「2050年カーボンニュートラル」という言葉が、今いろいろな業界で言われています。 正直、2050年ってまだ25年も先で、想像もつかない世界ではあるんですが、実際に船の設計をされるときに、そういった未来の目標はどのようにコンセプトや日々の業務に落とし込まれるんですか?
関さん(常石造船 設計本部 商品企画部 部長):
そうですね、現時点で2050年を見通すのは正直難しいです。ただ、その中で我々にできることは「選択肢を増やすこと」だと考えています。例えば、最新のKAMSARMAXは重油、メタノールどちらでも長い距離を走れる大きさの燃料タンクを持っています。そうすると、仮に将来、いずれかのバイオ燃料の方が安定して供給されるようになれば、そちらの方でゼロエミッションに対応できる。重油で走れない船と比べてゼロエミッションの選択肢を2倍持つことができる。我々としては、そうした未来の不確実性に備えることを視野に入れて船舶の新開発に取り組んでいます。
久保さん(Mers Line 代表):
それに船の寿命はだいたい20年から30年ぐらいです。そうなると、2050年に走っている船というのは、今作っていてもおかしくない。そう遠い未来のことではないんですよね。
――さきほど、藻類を使って船を走らせるには、コストと供給量のハードルがあるというお話を伺いました。一方で、カーボンニュートラルの実現も急務になっています。「経済性を確保する」という軸足と「環境負荷を低減する」という軸足、このあたりのバランス感覚についてはどうお考えですか?
関さん(常石造船 設計本部 商品企画部 部長):
環境負荷低減の取り組みは、必ずしも経済性と対立するものではありません。例えばデュアルフューエルのように、複数の燃料に対応できる船を設計しておけば、将来の不確実な燃料供給にも柔軟に対応できます。確かに初期投資はかかりますが、汎用性を持つ船にすることで、長期的に見ればコスト競争力のある選択肢になります。
むしろ、今後は排出するCO₂に対してコストが課される社会になることを考えれば、ライフサイクル全体で見たときに、初期投資をしたほうが結果的に経済的になる可能性は十分にあると考えています。

―― 日本館でKAMSARMAXのモデルシップを見た人に、どんな風に感じてもらいたいですか?
関さん(常石造船 設計本部 商品企画部 部長):
まずはやっぱり「かっこいいな」とか「これで世界の穀物を運んでいるんだ」と想像を膨らませてもらえたら嬉しいです。
一般の人にとって漁船やヨットを見ることはあっても、遠洋を走るKAMSARMAXのような商船を目にすることはほとんどないと思います。しかもこれは、将来を見据えて設計された「未来の船型」です。だからこそ、モデルシップとはいえ日本館でこの船に触れ、世界の物流を支える存在だと知ってもらえるのはとても意義のあることだと感じます。
―― 今日、造船所の見学もさせていただいて、こうした船を支える設計や運航の現場には、実に多くの技術や人の想いが詰まっているのだと実感しました。船そのものだけでなく、この海事業界にも興味をもってもらえたらいいですね。
関さん(常石造船 設計本部 商品企画部 部長):
そうですね。この業界はBtoB、つまり企業間の取引が中心なので、なかなか一般の方からは見えにくい世界です。でも実際には、人と人とのつながりが何より大切な業界だとも感じています。
いま、カーボンニュートラル達成に向けて、百年に一度あるかないかの変革期を迎えていると感じます。そんな時代にこの業界で仕事ができているのは本当に幸運なことです。
そして非常に難しい時だからこそ、一社で出来ることには限りがある。ちとせさんのように、これまで交わることのなかった分野の方たちとも手を組み、新しい可能性を切り拓いていくことが大切だと感じています。
誰かと一緒に挑戦していく中で、自分自身も誰かにとって「一緒に挑戦したい存在」になっていく。そういう経験ができるのが、この業界の面白さだと思うんです。日本館のKAMSARMAXがその入り口となって、次の時代を担う若い人たちがこの世界の一員になってみたいと思ってくれたら、これより嬉しいことはありません。

―― 大航海時代、商船は未知の大海へ乗り出し、香辛料や財宝、人々のロマンを運びました。そしてKAMSARMAXはまさにその系譜を引き継ぎながら、いまカーボンニュートラルという新たな航路へ挑もうとしています。日本館で出会うその船は、模型という姿を超え、私たちをどんな未来へと導いてくれるでしょうか?