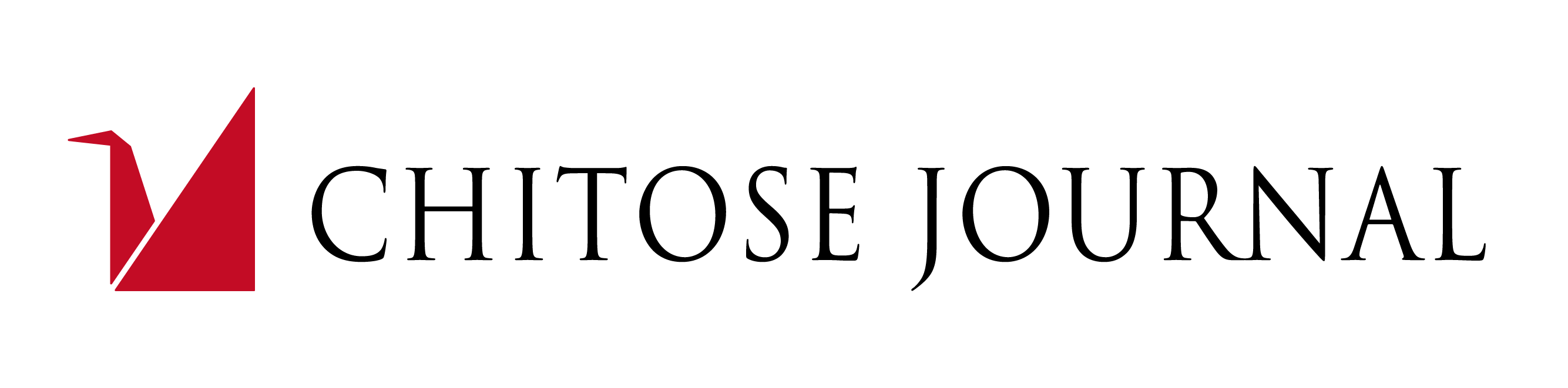青空、人混み、奇抜な建築群、遠くで響く異国の音楽。そこは夢洲、2025大阪・関西万博。目にも耳にも賑わいに満ちた会場内を少しゆくと、打って変わって日本館。一歩足を踏み入れれば、薄暗く静謐な空間に出迎えられる。その静けさの中で、躍動する「いのち」がある。見えないけれど、絶えず働き、日本館を支えている存在。それは小さな小さな藻類であり、日々その命に向き合う研究員たちだ。
そう、ここの展示は「生きている」。
日本館は「いのちと、いのちの、あいだに」というテーマのもと、生態系や資源の循環など、あらゆる「循環」を物語の軸に据えている。日本館ファームエリアでは、藻類が主役を務める。太陽光から光合成によって様々な有機物を生み出すこの小さな植物は、人類を化石資源依存を始めとする様々な課題から救い、循環型の未来を実現する可能性を秘めた重要なファクターとして紹介されている。この記事では、その「生きた藻類展示」がどのように支えられているのか、その舞台裏をのぞいてみよう。
いのちみなぎる「藻のカーテン」

緑のチューブが無数に張り巡らされた空間。ほの明るい光に包まれ、1本1本のチューブの中に「スピルリナ」という藻類が流れている。
この幻想的な美しさを支えているのが、地下に設けられた培養部屋だ。そこでは「フラットパネル型フォトバイオリアクター」と呼ばれる藻類培養設備があり、スピルリナは地下で育てられたのち、チューブをつたって展示空間へと送られる。
スピルリナは生きている。光や温度、栄養のバランスが少しでも崩れれば、鮮やかな緑はすぐにその輝きを失ってしまう。しかも地下で培養した藻を、地上のチューブに流し込み、育てながら見せる。そしてその状態を、半年の会期中ずっと保つだって?でも、私たちはプロだ。研究員たちが日々状態を見守りながら、生育環境を細やかに調整している。スピルリナを美しい緑のまま育て、展示空間に命を吹き込んでいる。
今、ここに輝いているのは、生きている緑だ。


ここは水族館、住んでいるのは、誰?

静かな水槽に目を凝らすと、細かな粒子が水中に揺れている。
ここは「見えない水族館」。その名の通り、目には見えにくい生きものが暮らしている。その正体は「ボツリオコッカス」。ボツリオコッカスは、その体内にたっぷりと脂質を蓄える性質があり、その油は石油と似ていて、燃料やプラスチックの原料、化粧品などへの応用も期待されている。
ひとつひとつは単細胞で、人の目には見えないほど小さいが、この藻は群れをなして暮らす。ぶどうの房のように集まることで、ようやく目視できるサイズになる。そうしてここ「水族館」で、ゆらゆらと漂う姿を見せてくれている。
この展示でのこだわりは、その粒をいかに見せるか。よく育ち、粒が大きくまとまったものを、来場者の視界に入る水槽の範囲に、ちょうどよく流す。そのために、光や流れ、温度など、細かな調整が繰り返された。
たぶん、そんなこと、言われなきゃ分からない―― が、
見えないところで気を利かせる。着物の袖口や襟元から、ちらりと色や柄をのぞかせる、そんな日本の粋にも似て。見過ごしてしまいそうな水槽の中にも、研究員たちのこだわりが息づく。


藻といえば「水を放置したら勝手に生えるもの」と思う人も多いかもしれないが、実は、単一の藻を狙って安定的に育てるのは非常に難しく、世界中の藻の研究者たちが頭を悩ませている。それなのに、無数のチューブに通したり、蓋もない水槽に入れたりして、長期間、美しく展示する。他に誰がそんなことできるというのか?
熾烈なパビリオン予約を勝ち取って、この展示の前までたどり着いたなら、どうか少しだけ足を止めて、小さな命の躍動と、それに向き合う人々に思いを馳せてみてほしい。