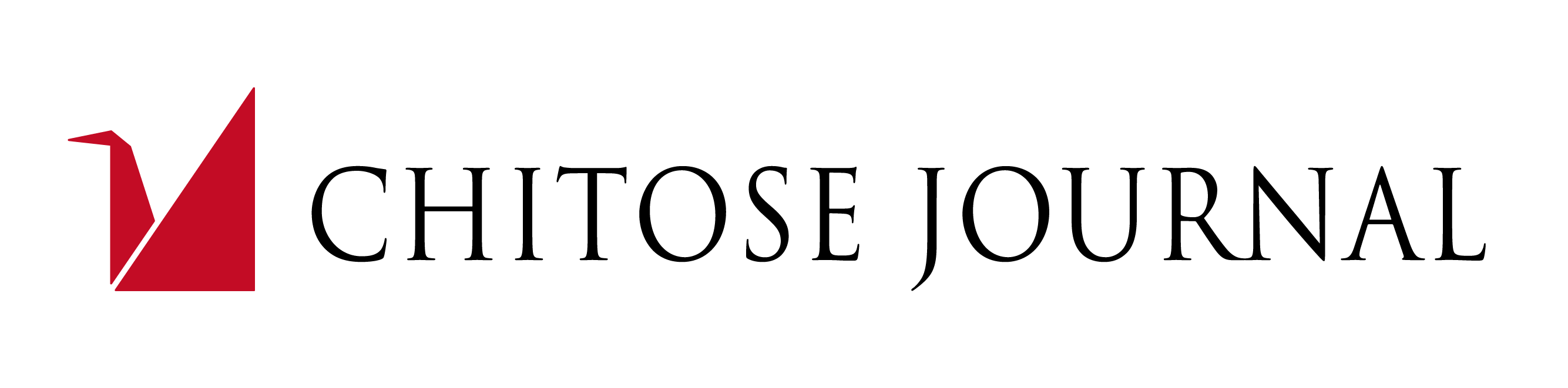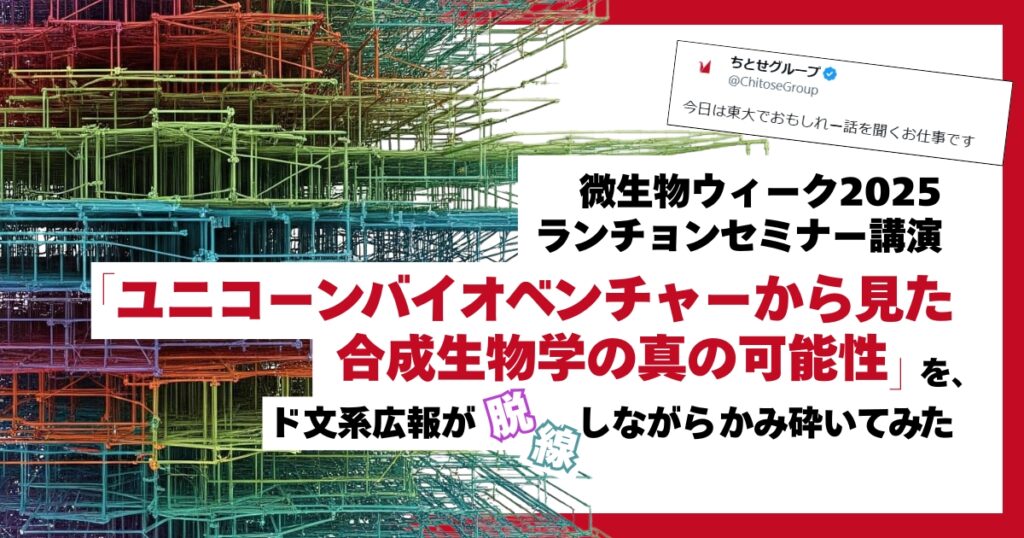
先日、東大でおもしれー話を聞いてきました。
7月29日、私が足を運んだのは、東京大学微生物科学イノベーション連携研究機構(CRIIM)が主催する「微生物ウィーク2025」。この日、ゆらゆらと立ちのぼる陽炎は、猛暑の太陽のせいか、日本最高峰の微生物ギーク達の知恵熱が、一ヶ所に集まりすぎたせいか・・・
とにかく、我らが若者のホープ尾島くんが、微生物ウィークで登壇するということで、その話を聞きに行ったのです。その講演内容は、ちとせが長年向き合ってきた問いとも重なるもの。生き物の分からなさとどう向き合うか。
講演タイトル「ユニコーンバイオベンチャーから見た合成生物学の真の可能性」は、いかにも賢そうな響きで少々怯みますが、ド文系広報・今野がかみ砕いてお届けします。ご安心あれ、中学の頃の私の理科の成績は4ですぞ。

合成生物学ってなに?
まずは文系よろしく、言葉の意味から理解を試みてみましょう。
合成 / synthetic
バラバラの部品を組み合わせて新しいものを人工的につくること。写真を切り貼りしてくっつける 「合成」写真、複数の電子音を組み合わせる 「シンセ」サイザー。
生物学 / bio(生命)+ logy(学問)
生き物のしくみやふるまいを解き明かそうとする学問。
合成生物学 / synthetic biology
生き物の仕組みを理解して、生命活動の新しい機能を人工的に作ろうとする学問。
合成生物学の難しさ
生き物の仕組みを解き明かそうという試みは、古くから行われてきました。ダーウィンやワトソンとクリック、ギークな先輩たちのおかげで、今では代謝や遺伝子、細胞分裂、ホルモンや酵素の生成など、生き物について多くのことが明らかになってきています。
そして、そんな生命活動の根幹ともいえる代謝の仕組みを示したものとして「代謝経路の図」というものがあります。路線図のごとく整理されたその図は、生体内の成分がどのように関連し、変化していくかを表しているのだそうです。
でも実際の代謝は、そんなに単純なものではありません。「一つの遺伝子をいじったら、思いがけないところに影響が出た」「フラスコサイズでは育てられるけど、大きなタンクに移したらうまくいかない」そんなことが、バイオの現場では日常茶飯事です。
生き物の代謝はもっと複雑で、時間や環境によっても表情を変える「三次元のネットワーク※1」なんだそう。それはとても奥深く、崇高で、研究としては非常に魅力にあふれるものなのでしょう。
※1 なんじゃそりゃ。同僚に聞いてみたところ「見る度に変わる立体地図みたいなもの」とのこと。え、「鬼〇の刃『無〇城編』」ってコト…!?(;ω;)
でもそんな底なしの謎を抱えた生き物を使って「ものづくり」しようとすると(=バイオものづくり)、途方に暮れてしまいます。機械であれば「部品や仕組みについて理解してから設計する」のが基本です。だけど、謎だらけの生き物が部品であれば「分かってないけど、やってみる」しかないわけです。
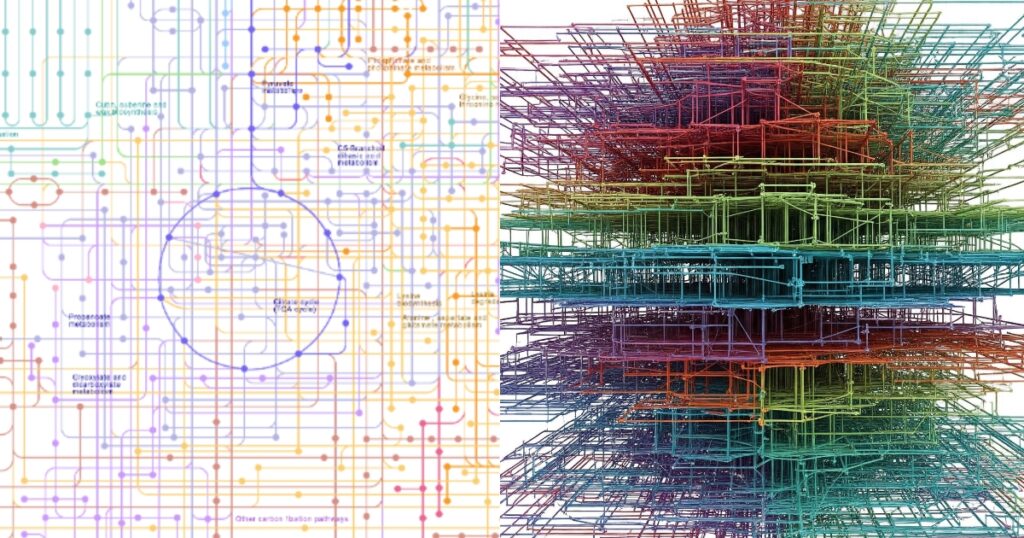
その難しさと、どう向き合うか
尾島くんの言葉に導かれながら頭に浮かんだのは「もしかしてバイオものづくりって、東洋的な頭の使い方がしっくりくるのでは?」ということでした。
西洋では、自然は人間が制御すべきもの。 菌にいたっては、殺すとか消すとか(殺菌、消毒)、物騒なスタンスで付き合ってきた歴史があります。一方で、東洋には漬物、味噌、納豆など、菌と共にある発酵文化が根付いています。それに、足つぼや漢方のように、バチっと説明できる理屈がなくても経験と全体感で、いい感じの効果を導き出す知恵もある。
ちとせのアプローチもその延長線上にあります。ちとせ研究所の前身、ネオ・モルガン研究所は、育種(=優れた品種を作り出すこと)を生業として創業し、「進化」という、生物が本来持っている環境適応能力に着目してきました。それは、人間が全てを制御して設計するのではなく、生き物が自発的に最適解を見つけて形を変えていくというアプローチ。ちとせに名前を変えた今も変わらず大切にしているのが「生き物をコントロールするのではなく、いい感じにマネージする」というスタンスです。
東洋的な在り方とAIの融合
さらにここ数年、ちとせのバイオものづくりの最前線に、AI制御技術が加わっています。これまで人の経験や感覚に頼っていた微生物の培養も、独自のセンサーで得た情報を元にAIが培養条件をフレキシブルに調整してくれる仕組みです。たとえば温度やpHといった培養条件の調整を、AIが行ってくれるのです。尾島くんによれば、培養による生き物の変化を数値で追い続ければ「次にどう振る舞うのか」を予測することができ、さらに、進化の方向性すら予測できるのではないかと考えているのだとか。
実際に、尾島くんが携わる発酵生産の現場では、ある微生物の培養をAIに任せてみたところ人間の(しかも長年経験を積んだ熟練者の)約2倍の生産性を叩き出してしまった実績もあるんです※2。
※2 さらっと書いていますが、これって将棋AIが名人を破っちゃったぐらい衝撃的なことです。“人が設計した最良条件を、ちとせのAIが凌駕 – 培養制御が難しい糸状菌でたんぱく質の生産性を2倍に向上 –”
そしてこのAI、人間には思いもよらないタイミングで培養槽の温度を上げたり、pHを下げたりします。それなのに、人間による調整を超える成果を出してしまう。しかもこれ、「なぜ今その調整を行っているのか」ということについては、分かっていないんです。衝撃、再び。
生き物の奥深さは、人間が完全に理解できる範囲を超えています。そしてAIが叩き出す優れた成果についてもその因果関係は分かっていません。それでもいいみたいです。分からないことを、分からないまま受け取って、いい感じの結果を出す。そんな東洋的な在り方とAIの融合こそ、尾島くんが言うところの「ユニコーンバイオベンチャーから見た合成生物学の真の可能性」なのかもしれません。
分からないと受け入れること
生きていると、私たちは「分からないこと」「答えの出ないこと」に幾度となく遭遇します。そんなとき、思い悩んでしまったり、誰かから借りてきたような言葉で納得感を埋めてみたりしがちです。
でも、私たちが過ごす毎日も、身体や精神の成長指数、属するコミュニティーの数、互いの信用度・・・、あまたの要素が絡み合う「三次元のネットワーク」なのだと思うのです。だとすると、分からないものは分からないと受け止めて、とにかく進んでみる。生き物という「謎だらけの部品」でも力を発揮してくれるように「分からないけど、とにかくやってみる」ことで拓ける道もあるのでは?と、今回の講演を聞いて、ド文系広報は考えたのでした。
さて、合成生物学の話が、いつの間にか人生論になってしまいました。分かっていただけたかな。分かってもらえなくてもOKです。分からないものだと、分かっていただけたのなら、満足です!