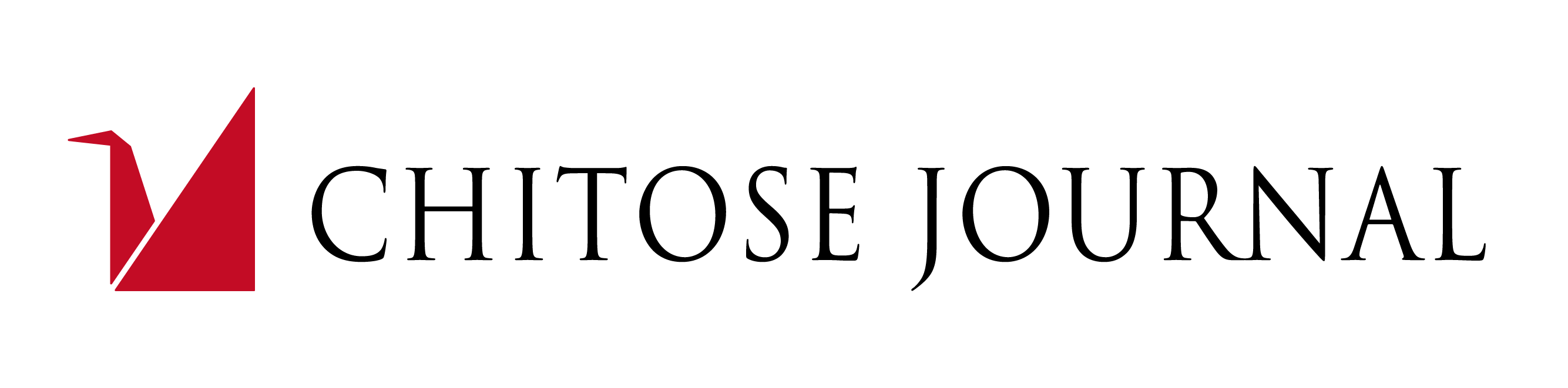「藻」と聞いて、何を思い浮かべますか?池に漂う緑色の物体、あるいは昆布やワカメといったお馴染みの海藻?
今、そんな藻類(そうるい)が、未来の暮らしを支える素材として注目されています。2025年大阪・関西万博、日本館では藻類がテーマのひとつ。そして、ちとせグループが主導するバイオを軸にした産業づくりを進める共創プロジェクト「MATSURI」は、日本館ファクトリーエリアで「『藻』のもの by MATSURI」をプロデュースしました。このショーウィンドウでは、藻類を素材にしたアパレル、化粧品、食品、塗料など、さまざまな「藻の物」が一堂に並びます。

微細藻類スピルリナを使ったフリーズドライ味噌汁を開発したのは、水産食品のリーディングカンパニー、マルハニチロ。その舞台は、2025年大阪・関西万博の日本館です。日本館では「いのちと、いのちの、あいだに」というコンセプトのもと、「循環」について考えさせられる仕掛けが随所に施されています。藻類味噌汁もそのひとつ。来場者は日本館で受け取った藻類味噌汁を味わい、体の中に取り込むことで、自らもその循環の一部となっていきます。
スピルリナは、タンパク質やビタミン、ミネラルなど豊富な栄養素を持ち、WHO(世界保健機関)をして「人類の21世紀の最も優秀なタンパク資源のひとつ」とも言わしめる食材です。そんな未来の食材に挑んだのは、戦前から冷蔵・冷凍技術で日本の水産業を支えてきた言わば「魚のプロ」。彼らが微細藻類を日常の一杯に落とし込むには、実は乗り越えるべき壁がいくつもありました。なぜマルハニチロは微細藻類に挑み、味噌汁という形にしたのか。そして、その先にどんな未来を見ているのか。開発を担った3人に、ちとせメンバーが話を伺いました。

今回お話を伺った方
今村 直哉さん(マルハニチロ 開発製造担当/調味料乾燥食品事業部乾燥食品課)
― 好きな食べ物は?「家系ラーメン!」
國永 史生さん(マルハニチロ 品質保証担当/品質保証部品質保証チーム)
― 好きな食べ物は?「お寿司(ブリやハマチの食べ比べがマイブーム)」
牧野 充宣さん(マルハニチロ 食品担当/業務用流通事業部事業一課)
― 好きな食べ物は?「え、お酒じゃダメですか…じゃあ、イカと練り物(笑)」

魚のプロが、なぜ「藻」を味噌汁に?
――まず、どうしてお魚の会社が微細藻類を扱うことになったのでしょうか。
牧野さん(マルハニチロ 食品担当):
きっかけは、2040年・2050年を見据えて発足した、次世代タンパク質を探る社内公募のプロジェクトでした。世界の人口増加や人々の食生活が急速に変わるなかで、これからの食を支えるには、新しいタンパク源が必要になります。そこで私たちが可能性を見出したのが、微細藻類でした。
國永さん(マルハニチロ 品質保証担当):
「プロテインクライシス※」という言葉があります。これまでマルハニチロは主に魚で良質なタンパク質を提供してきましたが、それだけでは増加し続ける需要を賄いきれなくなるかもしれない。そこで、このプロジェクトでは、これまで着手したことのない食材を使って、本当においしいものが作れるのか、そしてそれがビジネスとして成立するのか、という点を検証しています。
加えて、私たちが微細藻類に期待するもうひとつの観点は、食の安定供給の面です。というのも、天然の魚には、どうしてもボラティリティ(変動性)がつきまといます。例えば近年では、脂ののったサバが日本近海で獲れなくなってきています。魚は地球環境の変化に大きく影響を受ける生き物ですし、そこに乱獲、地政学的リスク、為替の影響も加わると、安定して仕入れるのが非常に難しくなります。 そうした不確実性を補う選択肢として、「環境や国際情勢などに左右されにくいタンパク源」が担う役割は今後ますます大きくなっていくのではと感じています。
※ 人口増加や食生活の変化によって、タンパク質の需要が供給を上回る状況が起こること。早ければ2030年に起こるといわれている。
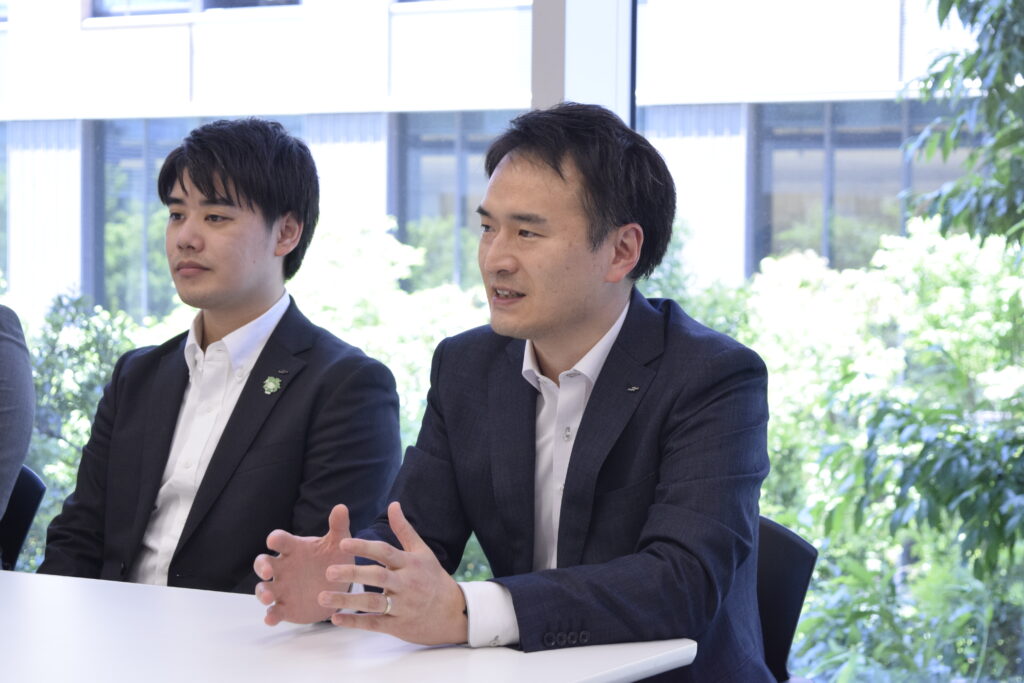
――なぜ、スピルリナを「味噌汁」という形にしようと思ったんですか?
牧野さん(マルハニチロ 食品担当):
実は、日本館で配布を行うには、いくつかの条件がありました。例えば、常温保存できること、数十万食規模で必要になること、その場で開封してすぐ食べられる形態は、避けたほうが良いという話もありました。会場内でなるべくゴミを出さないようにするためです。
そうした条件をすべて満たしつつ、日本を代表する食品として多くの人になじみがあって、私たちが自信を持って届けられるものを考えました。それが、フリーズドライの味噌汁でした。
――ここに至るまでに、やっぱり逆風ってあったんでしょうか?
牧野さん(マルハニチロ 食品担当):
社内からも「何やってんの?」とか「暇なの?」みたいな声もありましたよ!でも、「見とけよ!」って押し切りました(笑)簡単な道ではないことはもちろん分かっています。だけど、やるかやらないかなので、とことんやると強い意志をもって取り組んで来ました。

「藻類味噌汁~スピルリナ~」ができるまで
―― フリーズドライの藻類味噌汁ってどうやって作るんですか?
今村さん(マルハニチロ 開発製造担当):
なかなか想像がつかないですよね。でも、途中までは普通のお味噌汁の作り方と同じなんです。
給食センターのような大きな鍋でお味噌汁を作って、そこにスピルリナを投入します。ですがこのとき、水分は少なめに調整するんです。汁がシャバシャバだと具材が沈んで一食ずつ分ける際にばらつきが出てしまいますし、最終的に水分を飛ばすこともあり、初めから水分は少な目で作っておきます。

緑色のお味噌汁ができたら、鍋から四角い型に入れていきます。これがフリーズドライの型です。
型に流し込んだあとは一晩かけて凍らせます。この段階でもある程度水分は抜けるのですが、次に「真空凍結乾燥機」と呼ばれる潜水艦のような大きな装置の中に入れます。
この機械の中では、真空状態にすることで、氷が液体ではなく直接気体に変わる「昇華」という現象を利用します。つまり、凍ったままの状態から水分だけを気体として取り除いてフリーズドライにするのです。最後に厳正な検品を経て、パッケージに詰めて完成です。

――「藻類味噌汁~スピルリナ~」の特徴を教えてください。
今村さん(マルハニチロ 開発製造担当):
やはり一番の特徴は、スピルリナが入っていることですね。そして今回、「未来社会の実験場」という万博のコンセプトにも合致するよう、スピルリナの存在感が出るようにしました。スピルリナは熱に弱く、加熱すると緑色が茶色くなってしまいます。スピルリナの緑がきれいに発色するように加工の工程を工夫して、見た目のユニークさにもこだわりました。
具材には、淡い緑のキャベツ、深い緑のほうれん草も入っていて、スピルリナの緑と重なり合いながら、食感や風味の違いも楽しんでもらえると思います。
未来の当たり前を、いま仕込む。
ここまでは、「藻類味噌汁~スピルリナ~」が生まれるまでの物語。では、それをどう未来に結びつけていくのか。議論は次のフェーズに移ります。
――将来、微細藻類を「当たり前」の食材にしていくには、どれくらいの生産量が必要で、どんなステップが必要だと思いますか?
國永さん(マルハニチロ 品質保証担当):
「プロテインクライシス」について本気で考えるなら、食品の大部分を微細藻類が担うくらいの規模感が将来的には必要になると思っています。でも、それっていきなり0から100に全部が変わる話ではないんですよね。イメージとしては、車を例に挙げるとハイブリッド車の普及に近いです。短期間で全ての車が電気自動車に置き換わる訳ではないことと同じです。
食の分野も既存の食材とうまく折り合いをつけながら進化していくのだと思っています。私たちは、マグロやステーキのおいしさを知っているので、それを完全に無くすというのは現実的ではありません。目指しているのは、藻類が担える役割をしっかり見極めて、新しい選択肢として社会に届けていくことだと考えています。
牧野さん(マルハニチロ食品担当):
私たちは食品会社なので、まずは「おいしいから食べてみよう」と思ってもらえることが第一歩だと思っています。スピルリナの栄養価は素晴らしいですが、おいしくなければ選ばれない。そして後から「そういえば体調がいいな」とか「実は身体に良かったんだ」と気づいてもらえたら理想的です。
最終的には日々の食卓シーンに入り込みたいですね!お味噌汁しかり、毎日の食卓で。例えば、微細藻類を原料の大半に使ったハンバーグや、魚肉ソーセージなんかもいいですね。お菓子のジャンルでは、抹茶味のおかげで緑色が既に浸透しているので、案外受け入れられやすいかもしれません。

――最後に、万博という機会を通じて、来場者や次の世代に伝えたいことを教えてください!
國永さん(マルハニチロ 品質保証担当):
大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」ですが、万博という煌びやかな舞台にしては、「命」というとてもプリミティブなテーマであることが印象的です。
そして命につながる食の仕事をしている私たちだからこそ、今回そんな万博の機会に携わることができたのは非常に光栄ですし、微細藻類という食材をきっかけに、多くの人に未来の食について考えてもらえたらいいなと思っています。
牧野さん(マルハニチロ食品担当):
実は私は、20年前の「愛・地球博」にも関わった経験があるのですが、その当時、難しいといわれていた技術が2025年現在では当たり前になっている例がいくつもあるんですよね。
今、世の中に浸透している「当たり前」も始めたときは大変だったはず。でも普及し出したらきっと広まるのは一瞬だと思うんです。今は乗り越えるべき課題もまだまだありますが、20年前の万博に思いを馳せて、そして20年先の未来を想像して、ニヤニヤしています。微細藻類が当たり前の食材になった未来で、「そういえば万博で藻類味噌汁を配ってたね」なんて、誰かの思い出になったら面白いですね!